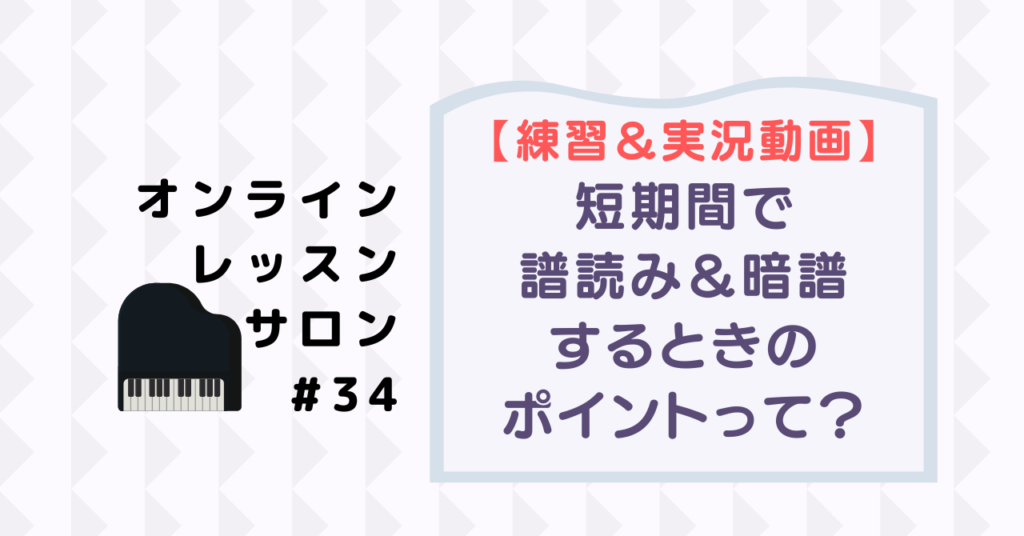新しい曲を始めよう!
というとき、
譜読みや暗譜、内容を深める練習…どんなふうに進めますか?
たぶん一般的には、
譜読み→だんだん弾けるようになる→内容を深めつつ→暗譜できてくる→さらに内容を深めつつ→形になってくる
みたいな順が多いんじゃないでしょうか?
でも、場合によっては
譜読みしながら同時進行で暗譜
とか
ほぼ初見でもう本番
とか
移動中に楽譜を読みこんでいきなり本番
なんてこともあったりします(3つめはわたしは未体験ですが…)。
そんなわたしも、事情により「譜読みしながら同時進行で暗譜、仕上げ」を行わないといけない状況がありました。(※「仕上げ」という言葉がしっくりこないのですが、便宜上使っております…)
そんな状況のわたしが実際に、ピアノの練習やほかの時間に実践してみたことをまとめました。
(ひとこと)音楽はなんでも効率よくやれば良い、というものでもありませんが、短時間でできるだけ濃いことができれば、また別のものを生み出す時間をつくれますので有意義だと思っています。
練習の具体的な方法になるので、文章だけだと少しわかりにくいかもしれませんが…
短時間&短時間で譜読み、暗譜しないといけない事情のある方は、ご参考になりましたら幸いです。
今回のようなイレギュラーなケースではなく、じっくり曲を仕上げていく各ステップについてまとめている記事です。
1曲をどんなふうに練習して仕上げていくの?選曲から本番までの長〜い道のり
 【ピアノ練習の山登り!】1曲をどんなふうに練習して仕上げていくの?選曲から本番までの長〜い道のり
【ピアノ練習の山登り!】1曲をどんなふうに練習して仕上げていくの?選曲から本番までの長〜い道のり
暗譜のコツや方法をあらゆる角度から紹介している記事です。
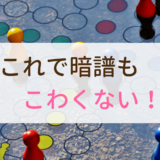 暗譜がこわい?苦手を解消する17の練習メニュー
暗譜がこわい?苦手を解消する17の練習メニュー
もくじ
短期間で譜読みと暗譜を同時に行うときのポイント
事情により譜読みと暗譜を同時進行中。
・小節、フレーズの単位を見る
・規則性のある部分と不規則な部分を見分ける
・外声と内声の音程差を覚えながら響きを確認
・体の流れも一緒に覚えるいろいろあるけど、1番大事なのは一つ一つの音のはたらきに頭も心も耳も集中すること…
— さいりえ / 崔 理英 ( Piano ) (@smomopiano) February 5, 2020
小節、フレーズの単位を見る
まず、曲の構造を確認します。
暗譜を急がない場合は、ざっと全体を何度か弾いて、雰囲気を感じたり大らかに音楽をとらえたりすることもあるのですが、暗譜を急ぐ場合はまず構造。
譜読みしながら。もしくは、譜読みする手を止めて、楽譜を見つめます。
- 何形式なのか(A-B-Aなどを大きく把握)
- 何小節単位で音楽が動いているのか(場所によって違う。1,2,4,8などが多いがそれ以外も)
- 和声の進行はどんなまとまりになっているのか(シンプルな進行→◯小節目で大きなカデンツ、など)
これは街歩きなどでも同じです。
旅行に来て、ぶらぶらと歩くのも楽しいけれど、効率よく観光スポットをまわるなら事前に地図を読み込んで行きたいスポットをチェックしておきますよね。
曲も、ぶらぶら弾くのも楽しい時間なのですが、早く覚えたいのであればできる限り早い段階で構造を理解することです。
構造を理解することで演奏の質も上がります。
なぜ演奏に「構成力」が必要なの?長いピアノ曲をまとめるのが苦手なあなたへ。
 なぜ演奏に「構成力」が必要なの?長いピアノ曲をまとめるのが苦手なあなたへ。
なぜ演奏に「構成力」が必要なの?長いピアノ曲をまとめるのが苦手なあなたへ。
規則性のある部分と不規則な部分を見分ける
先ほどの「小節、フレーズの単位」が全体的な地図だとすれば、次は細かい道や曲がり方を確認しておくイメージです。
規則性のある部分と、不規則な部分を見分けてから譜読み、暗譜すると効率がアップします。
規則性のある部分とは?ゼクエンツ(反復進行)や、同じ伴奏形が続く、など、比較的覚えやすい部分です。
かならずしも反復形でなくても、あなたにとって「これは自然に耳と手が動いていくなぁ」と思える部分もそうです。
同じ作曲家の曲をたくさんやっていると、はじめての曲でもスッと弾けたり和音が想像できたりしますよね?そんな部分です。
規則性や馴染みがある部分は、比較的覚えやすいですよね(もちろん油断は禁物です)。
流れに乗せながら弾き、ポイントを確認しつつ覚えていきます。
不規則な部分とは?前後の流れや自分の経験からは予測がつかない部分のこと。
予測がつかない部分はとくに意識的に覚える必要があります。
これらを区別しておかないと、ある程度暗譜した後でも、気持ちよくサラサラ〜と弾いているはずが突然わからなくなる、突然止まりそうになる、という事態になりやすいです。
 さいりえ
さいりえ
・外声と内声の音程差を覚えながら響きを確認
つぎは、かなり具体的な話になります。
音程差を覚えることは、意識的に行っています。
- 和音が多い曲だと、各音の音程差。
- 伴奏形が複雑な曲なら、バスと次の音との音程差。
- 多声的な曲なら、声部間の音程差。
- メロディの音程も覚えたりします。
3度や8度(オクターブ)は比較的自然に覚えられます。
2,7度もめずらしい響きなので覚えやすい。
4,5,6度が、なんとなくの暗譜だとごっちゃになりやすいので、頭や手、そして耳に刻み込みながら覚えます。
・体の流れも一緒に覚える
暗譜は頭の中だけで覚えるわけではありません。
- どのように腕を導いていくか
- 広い音域で弾くとき、体の開き具合や支えはどんな感覚か
- 先ほど覚えた音程を、実際の指や手の間隔にあてはめたとき
- 曲の中で、自分の内面や呼吸がどのように変化・変遷していくか
など、曲を弾いているときの体や心の状態を観察し、それらが自分の中にしみこむように覚えていきます。
暗譜の記憶をできるだけ素早く定着させるためのポイント
続編
・夜寝るときなどにその日のポイントや曲そのものを頭の中で反芻する(なんとなくではなくて指や体の動きもイメージしながら)
・前の日に濃くやった部分を次の日に確認/次の日は新たに別の部分を濃く
・試しに楽譜を閉じて弾いてみるタイミングをふだんより前倒しに(必ず弾けなくてもいい) https://t.co/WyhzHbZyZD
— さいりえ / 崔 理英 ( Piano ) (@smomopiano) February 6, 2020
つぎは、ステップ1で行ったことを定着させるための行動です。
・夜寝るときに、その日のポイントや曲を頭の中で反芻する(なんとなくではなくて指や体の動きもイメージしながら)
人間、眠るときに記憶が定着することがわかっています。
あなたも、ある日の練習ではしっくりいかなかったことが、次の日になるとスーッとできたという経験はありませんか?
うまくいったりいかなかったり、急にできるようになったり…その繰り返しで、上達していくわけですよね。
暗譜を急ぐときは、ふだんよりも意識的に、夜寝るときやその他のちょっとしたスキマ時間に、曲を頭の中で反芻(「はんすう」=くりかえし考え、味わうこと)をします。
 もも
もも
このときも、ぼんやり思い出すのではなく、楽譜の像や指・体の動きもイメージしながら思い返すと、次の日に少しでも定着しやすくなります。
・前の日に濃くやった部分を次の日に確認/次の日は新たに別の部分を濃く
つぎに練習スケジュールについてです。
前の日に◯〜◯小節目をしっかりやった場合、次の日にそこをざっと確認します。
ステップ1の要領でみっちり覚えていくと、次の日にもある程度記憶は定着していますが、ここで離れてしまうとまた忘れやすいです。
2日、3日と、確認しながら連続してくことで、本当に定着してきますし、それでも曖昧な部分は要チェックです。
そして同時進行で、新しい部分も覚えていきます。
・試しに楽譜を閉じて弾いてみるタイミングをふだんより前倒しに(必ず弾けなくてもいい)
曲を練習していて、「よし、ちょっと暗譜で弾いてみようかな」というときってありますよね?
そのタイミングを、いつもより前倒しにします。
完璧に覚えられていなくてもかまいません。やってみることで、
- 暗譜があいまいな部分
- いちおう覚えているけど、頭の中で系統立てられていない部分
- 頭の中で音楽は流れているけど、手や心がスッと動かない部分
など、いろいろなことに気づくことができます。それを、次の練習に役立てます。
録音してみるのも良いですね。
暗譜で通してみるのも良い確認練習になります。「通し練習」にもいろいろ!
本番に向けての通し練習。3種類の目的と方法〜ただ通すだけじゃダメ!〜
 本番に向けての通し練習。3種類の目的と方法〜ただ通すだけじゃダメ!〜
本番に向けての通し練習。3種類の目的と方法〜ただ通すだけじゃダメ!〜
短期間で暗譜するための、その他のミニポイント
ここまで紹介したこと以外の、ミニポイントをご紹介します。
ミニといっても、大事なことばかりですのでご参考になればと思います…!
楽譜は同じものを使う
本来、楽譜はいろんな出版社や校訂者のものを見比べていくことで勉強が深まりますが、短期間で暗譜する場合は、少なくとも暗譜のための楽譜は1冊に決めたほうが良いです。
曲を暗譜するのって、音だけを耳や頭の中で暗譜するのではなくて、「楽譜の画像」を写真のように覚えていたりするんですよね。
人によって暗譜の感覚は違うと思いますが、わたしは頭の中でページをめくっていくように覚えている曲もあります。
そのため、いろんな楽譜を使っていると、その記憶が揺らいでしまいます。
短期間で暗譜する場合は、楽譜を一冊に決めて、その画像ごと覚えていくのがおすすめです。
(ただし暗譜以外の目的で複数の楽譜を見るのは、むしろ良いことです!)
「言葉」でも覚えていく
音楽は「音」ですし、ピアノの演奏の中には「ことば」はありません。
でも、意識的に「ことば」にしていくことで、記憶がくっきりします。
- たとえば、6度離れているなら「6」という数字を口に出して覚える。
- A-durになるなら、「A」という文字を楽譜に書いて、その文字も覚える。
というように、ふわっと覚えるのではなく、あらゆる角度からガッチリ頭に刻み込んでいきます。
こうすることで、短期間でもかなり覚えやすくなります。
途中からでも弾けるようにしておく
途中からでも暗譜で弾けるようにしておきます。
途中から弾くのが苦手…という人もおられるかもしれません。
ですが、ここまで書いたことを実践していけば、きっと途中からでも記憶の糸を見つけてパッと弾けるようになると思います!
まとめ〜短期間で暗譜するには、音楽基礎力もアップさせよう!〜
この記事では、短期間で暗譜するためのステップをご紹介しました。
ここまで書きませんでしたが、だいじなこととして
- 一つ一つの音・要素をよく感じて聴く
- 音楽の基礎力をアップさせる
というのがあります。
基礎力をアップさせることで、同じことを達成するための時間は大幅に短縮できます。
基礎力アップのためのあらゆる方法や視点については、当ブログやLINEでも発信していますので、ご参照いただければと思います。
今回のようなイレギュラーなケースではなく、じっくり曲を仕上げていく各ステップについてまとめている記事です。
1曲をどんなふうに練習して仕上げていくの?選曲から本番までの長〜い道のり
 【ピアノ練習の山登り!】1曲をどんなふうに練習して仕上げていくの?選曲から本番までの長〜い道のり
【ピアノ練習の山登り!】1曲をどんなふうに練習して仕上げていくの?選曲から本番までの長〜い道のり
暗譜のコツや方法をあらゆる角度から紹介している記事です。
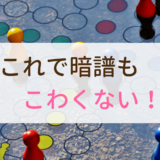 暗譜がこわい?苦手を解消する17の練習メニュー
暗譜がこわい?苦手を解消する17の練習メニュー