バッハのシンフォニア。
一人の生徒さんのレッスンを長年続けるときでも、このシンフォニアは一つの関門です。
2声から3声の勉強に移行するステップには挫折ポイントも多く、また楽しくやりがいのあるところでもあるのです。
そんなシンフォニアですが、小学生や中学生のコンクールの課題となることも多いですよね。
15曲、どれを選んでも良いよと言われると、逆に迷ってしまいませんか?
そんなあなたに、1曲ずつの解説とおすすめポイントを書いていきます。
一部、わたし自身の演奏・解説動画も載せていますので、ご参考になさってください。
(参考記事)シンフォニアの譜読み・練習方法の【徹底解説】はこちら
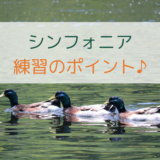 バッハのシンフォニアの譜読み・練習方法を徹底解説!フーガにも生かせるよ
バッハのシンフォニアの譜読み・練習方法を徹底解説!フーガにも生かせるよ
※ 項目別でなく、「○番のコメントを読みたい!」という方は、以下の「もくじ」から番号をクリックしてください。
もくじ
シンフォニアの習い始めにオススメの曲(6番, 12番)
誰にでも、一番始めはあります。
- インヴェンションを15曲終えた。
- もしくは、インヴェンションはまだ半分くらいだけど、今度の発表会・コンクールにはシンフォニアにチャレンジしてみよう!という人もいるかもしれません。
そんな人におすすめしたいのがこの辺りです。
シンフォニア第6番 ホ長調(動画あり)
分析&解説動画はこちら↓
難易度が低いということはないのですが、8分の9拍子で1小節あたりの音数が少ないので、3声に初めてチャレンジするときにも、比較的 意味を理解しやすい曲です。
主題もシンプルなので、「このように弾けたら良いだろうな」という理想像も浮かべやすいです。
こんな人にオススメ!
美しい響きを持つ曲なので、温かな音色を持つ人や流れるように歌うことがきれいな生徒さんに勧めることも多いです。
本当に初めてシンフォニアを譜読みするときには、ぜひ意味を理解して(教えてもらって)地道に丁寧に見てください。
自己流でざーーーっと最初から最後まで繰り返し弾く、というのは一番オススメできません。
始めは8小節からでも良いので、丁寧に、音の重なりや指の上げ下げ(音を保持する、離す)を楽譜と共に理解してゆっくり弾いていきましょう。
千里の道も一歩から。
(具体的に進めるには)シンフォニアの譜読み・練習方法の【徹底解説】はこちら
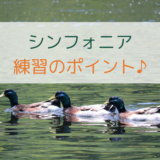 バッハのシンフォニアの譜読み・練習方法を徹底解説!フーガにも生かせるよ
バッハのシンフォニアの譜読み・練習方法を徹底解説!フーガにも生かせるよ
シンフォニア第12番 イ長調(動画あり)
分析&解説動画はこちら↓
第6番に比べると音数も多く、テンポもやや速めの曲ではあるのですが、こちらも比較的取り組みやすい曲です。
嬉遊部(主題部との繋ぎの部分)が比較的シンプルに書かれているのがわかりやすいように思います。
(あくまで勉強しやすいというだけで、易しいわけではありません)
また、3声の分配が右手に多めになっているのも(右で2声を弾き、左で1声を弾く)、多くの人に弾きやすいポイントかと思います。
とは言え、いくつか注意深く練習しなければならない箇所もあり、じっくりゆっくり、こちらも意味を理解してやっていきたい曲です。
とくに3小節目にいきなり左手で2声を奏する部分や、以降、右手の2声でシンコペーションの掛け合いをしている部分は、こちらも自己流で音の頭だけ出していると大変です。
音価(音の長さ)とバランスがとても重要です。
こんな人にオススメ!
と、重要ポイントもあるのですが、全体的には明るく華やかな曲調なので、けっこうオススメです。
基本的な指の働きがきっちりしている人や、明るい曲調が得意な人に合うと思いますよ。
3声を弾く、聴くことに少しずつ慣れてきたら(1番, 10番, 8番)
3声に慣れてきたら、どんどん曲数を重ねて経験を積んでほしいと思っています。
前の曲の復習をしながら、どんどん経験を積むのに良い曲は、こちらの3曲。。
シンフォニア第1番 ハ長調(動画あり)
演奏動画はこちら↓
分析&解説動画はこちら↓
第1番ということで始めに取り組む人も多くおられるかもしれません。
それまでに、ある程度理解と経験があればそれも良いと思います!
でも、3声について慣れていない場合は、数曲勉強してから第1番に入るのが良いと私は思います。
この曲は、主題はシンプルな音階と音型の組み合わせですが、音数が多いのと、大きな流れを必要とするため、一定の技術と大きな視点が必要になります。
こんな人にオススメ!
主題の長いフレーズ感を大切にしながら、同時に出てくるモチーフのリズムやキャラクターを表現し、またハ長調から様々な調に転調していく展開を、大きくまとめたい曲です。
シンプルな曲なだけに、タッチの正確さや美しさが優れている人にもオススメです。
シンフォニア第10番 ト長調(動画あり)
演奏動画はこちら↓
分析&解説動画はこちら↓
こちらも、ゆっくり弾けば第6番や第12番くらい勉強しやすい方かと思いますが、ト長調で、主題の持つ方向性も考えると、生命感のある演奏が求められます。
また、途中には2声が重なって交差しているため(上の声部が下の声部よりも低い音になる部分)、指の使い方が独特になる部分があります。
こんな人にオススメ!
それらを正しく自然に弾き分けることができ、全体は爽やかに弾ききることがポイントとなります。
生き生き弾くのが得意な人にもオススメです。
丁寧に練習できれば、早い段階でチャレンジしても良い曲ではあります。
シンフォニア第8番 ヘ長調(動画あり)
分析&解説動画はこちら
とてもシンプルで親しみやすい曲です。
主題自体が、動きのあるリズムを持っているので、それを感じて弾きたい曲ですね。
3声の動きも勉強しやすく、いろいろな形が出て来るので勉強になります。
中庸なテンポで爽やかさと落ち着きが出せると素敵な演奏になるでしょう。
こんな人にオススメ!
この曲も、丁寧に練習できれば早い段階で選曲しても良いと思いますが、トリルが意外と?ネックになるので、トリルに苦手意識のある方は少し後から。
トリルもスッと弾ける人なら早めに勉強しても良いのではないでしょうか。
シンフォニアに自信が出てきたら。総合的な曲(3番, 4番, 7番)
シンフォニア第3番 ニ長調(動画あり)
演奏動画はこちら↓
分析&解説動画はこちら(途中で切れています、すみません)
この曲は全体的なまとまりもよく、明るく落ち着いた曲調なので、よく選ばれる曲の一つです。
それなりのテンポで弾かれるため、指さばきもやや複雑なところがあり、特に右手がスムーズにキッチリと歌えるかということはポイントの一つとなります。
こんな人にオススメ!
内容の充実度もあり、シンフォニアに慣れてきてしっかりまとめられる人におすすめの1曲です。
シンフォニア第4番 ニ短調(動画あり)
演奏動画はこちら↓
分析&解説動画はこちら↓
こちらも第3番と並んで充実した曲です。
ただ、同主調で全く曲調が違います。
第4番はやや物憂げな性格を持ち、第9番で述べたような半音階の下行も途中で出てきます。
この半音階はレガートで弾くことを私はおすすめしています。
その場合、主題のアーティキュレーションとは対照的に、美しいコントラストを付けられると素敵です。
こんな人にオススメ!
短調特有の美しい和声が多く出てきますので、一つ一つの音の重なり、響きを味わいながら弾きたい曲です。
3番と同じく、しっかりまとめつつ、よく歌える人にもオススメです。
シンフォニア第7番 ホ短調(動画あり)
分析&解説動画
この曲もかなり大曲です。
3度で動く音程や6度の音程、また8分音符のモチーフに加え、途中から16分音符のモチーフが多用されます。
技術的にも様々なポイントがありますので、じっくり勉強したい曲です。
こんな人にオススメ!
音楽的にもとても美しいので、3声を弾くということに、手も耳も頭にも ある程度余裕が出てきてから、落ち着いて演奏したい曲です。
この曲の内容に共感し、重音をしなやかに奏することができる人にはぜひチャレンジしてもらいたい曲です。
拍子感も重要。いろいろなタイプの曲(2番, 11番, 13番)
さて、残り3曲となりました。
ここに挙げる3曲も、発表会やコンクールでよく弾かれる素敵な曲ばかりです。
それぞれに特徴がありますので、ご紹介していきます。
対位法の難易度としては、一つ上に挙げた3曲の方が難しいです。
ですが以下の3曲はキャラクターが強いので、それを表現できることも重要です。
シンフォニア第2番 ハ短調(動画あり)
分析&解説動画はこちら↓
8分の12拍子で、落ち着いた美しい主題を持ちます。
実はこの主題、1曲中でたったの数回しか出てこないのです。
その他は、主題の前半部分や発展型が繰り返されていきます。
和声、調性の移り変わりがとても美しいので、一音一音を大切に聴いて弾きたい曲です。
こんな人にオススメ!
この曲は拍子感も重要です。複合拍子独特のリズム感を持ちながら、2小節以上を一つにとらえる大きな呼吸がほしいです。
長いトリルも特徴です。
対位法はそこまで複雑でないので、まだ3声に慣れていないうちでもチャレンジすることができるでしょう。
シンフォニア第11番 ト短調(動画あり)
分析×解説動画はこちら↓
この曲もけっこう変わった構成をしていますね。
8分の3拍子で、短いモチーフの組み合わせで出来ています。
舞曲のような空気感を持ち、憂いのある曲ですが、甘すぎず、どこか凛とした部分を持って弾きたい曲です。
こんな人にオススメ!
この曲は8分音符の長さ、表現がなかなかセンスの問われるところです。
上に挙げた第3,4,7番などに比べると、手が小さめでも表現しやすいので、感受性が強く美しい音を持っているけれどまだ手がガッチリ大きくない、というお子さんにもおすすめです。
シンフォニア第13番 イ短調(動画あり)
分析&解説動画はこちらです↓
おもにペダルについて、13番を弾いています。↓
こちらも8分の3拍子。
この曲は、曲の中で主要なモチーフがどんどん新しく登場するのが面白いです。
始めの主題は、4度の上行→下行のシンプルな形ですが、これがなんとも美しい。
2つめは、分散和音でシンコペーションの形です。音楽に動きが出てきます。
そして3つめのモチーフは、舞曲のような躍動感を持ちます。
それぞれが個性的なので、インパクトの強い曲で、おすすめです。
しかし後半、左手で出てくる主題がかなり難易度が高いです。
- 指の独立
- コントロール
- 6度音程のポジション
- 必要な分だけペダルを入れる力
などなかなかここが難関です。
こんな人にオススメ!
テクニック、内容ともに美しくまとめられると素敵な曲です。
シンフォニアの中でもとくに難易度の高い曲(14番, 9番)
ここまで、11曲をご紹介してきました。
残りの4曲(5,9,14,15番)は、やや変わった書法の曲や、飛び抜けて難易度の高い曲となります。
この中で、第15番は条件が合えばオススメの選曲ですが(詳しくは後述)、あとの3曲は理由がない限りいきなり選ぶのは私はおすすめできません。
もちろん、レベルアップしたい、シンフォニアの勉強の集大成にこれを弾きたい、など理由があれば良いと思います!
最終的には、ぜひ経験してほしい曲ばかりです。
ではまいりましょう。まず、14番と9番についてです。
シンフォニアはどの曲も一定以上の技術や理解が必要ですが、中でも特に緻密に書かれていて曲の完成度・難易度が高いのがこの2曲です。
平均律の易しめの曲より、格段に演奏が難しいと思います。
シンフォニア第14番 変ロ長調(動画あり)
演奏動画あり。14番だけの解説動画は今後撮る予定です↓
(クリックしていただくと14番の演奏からスタートします)
とても穏やかな主題で親しみやすい雰囲気なのですが、後半かなり入り組んでおり、声部を的確に弾き分け歌わせるのはかなりの技術と理解を必要とします。
この曲を演奏するには、「フレーズ」「アーティキュレーション」つまり音楽の呼吸、文脈がとくに大切です。
こんな人にオススメ!
1声ずつ聴いて、よく表現を検討しながら丁寧に練習したい曲です。
作品の雰囲気としては穏やかですので、難しさを感じさせずに大きな音楽観で・・・それでいて細部を正確に弾きたいですね。
この曲は、普段のレッスンでもシンフォニアの経験をかなり積んでから弾いてもらっていますし、コンクール等でこの曲を選曲するときは相当の力を持っていると思うときですね・・・。
力がついてきた!平均律に進もう!くらいのレベルでぜひ集大成の演奏を聴かせてほしいです。
シンフォニア第9番 ヘ短調(動画あり)
こちらの動画内に演奏動画あり。9番だけの解説動画は今後撮る予定です↓
こんなに構成の密度も精神性も高い曲がシンフォニアの中にあるとはすごいと、いつも思います。
この曲は主題の提示が行われる時、いつも3種類のモチーフが緊密に重なり合って出てきます。
最初に右手で奏される主題が重要であることはもちろんなのですが、左手の半音階、また途中から出てくる呼びかけてくるようなモチーフも同じく重みを持っています。
このフーガを演奏するには、ただごとではない理解と集中力と技術を要します。
それだけではなく、この曲の持つ「精神性」がさらに輪をかけます。
ヘ短調という重みを持つ調性。
半音階下行のモチーフは「イエス・キリストが十字架を背負いゴルゴダの丘を一歩一歩進む足取り」とも言われています。
音の深さ、表現の深さが求められます。
この曲もやはりコンクール等の選択肢から外れている場合があるのも、うなずけます。
サラサラと技術面をクリアして弾いても、全く満足できない曲です。
こんな人にオススメ!
奥深さを追求し、この曲にしっかりと気持ちと時間を注ぐ思いでぜひ勉強してみてください。
シンフォニアの中でも特殊な曲(5番, 15番)
さいごに、ちょっと特殊な曲を挙げます。
シンフォニア第5番 変ホ長調(動画あり)
こちらの動画内に演奏動画あり。5番だけの解説動画は今後撮る予定です↓
シンフォニアを数曲勉強した生徒さんには、この第5番の楽譜を見せて「これまでの曲と何が違うかわかる?」と聞いてみます。
だいたい、
- 左手がずっと同じ
- 左手にテーマが出てきてない
- 右手がはじめから終わりまで会話になってる
などと答えてくれます。
これらはすべて、この5番特有の特徴です。
他の曲は、3声それぞれが対等に独立しています。
各声部の個性はあるのですが、基本的にはモチーフを対等に扱い、順に奏していくんですね。
ですがこの5番は例外。
この曲は、「ソプラノ+アルト」の2声と低音部1声、つまり「2+1」の組み合わせになっています。
鍵盤楽器の3声フーガという対位法のために書かれたのではなく、
旋律楽器(管楽器や弦楽器)2本と通奏低音(チェンバロなど)のアンサンブルを想定して書かれたからでしょう。
つまり、曲の様式が違うのです。
コンクールでシンフォニアの課題が出るときは「3声の弾き分け」も大きな重視ポイントになっていますので、この第5番は課題から省かれることもしばしばあります。
省かれていない場合も、この第5番を選ぶのはなかなかチャレンジャーかもしれません。
こんな人にオススメ!
装飾音は当時の様式を映し出して自然におしゃれに、旋律楽器の優雅な対話、同じリズムが延々と続く通奏低音のゆったりとした3拍子の拍感を感じて。
バロック時代の音楽が好き!バロック音楽をいろいろ聴いている、という方にぜひオススメですね。
素敵に弾けるととても良い曲ですね。
シンフォニア第15番 ロ短調
こちらも、第5番ほどではないですが、少し特殊です。
16分の9拍子、つまり大きな3拍子で書かれており、
- 16分音符による舞曲のような動き×旋律のある部分
- 32分音符による器楽的で鮮やかなパッセージ部分
の組み合わせで書かれています。
16分音符の部分は、「1+1+1」ではなく「2+1」の組み合わせになっています(第5番と異なるのは、組み合わされる声部がその度に違うということです)。
32分音符部分は華やかで、対位法的というより技巧的、トッカータのようです。
このように独特の面が多く、やはり他の13曲と比べると特殊な1曲であると言えるでしょう。
ただ、この曲はコンクールで演奏されることも比較的多いですね。
こんな人にオススメ!
まだ3声に慣れていないけど、リズム感や指の俊敏さは持っている・・・という段階の方でも選曲しやすい良さがあります。
キリッとリズムや音を立てながらも、ロ短調の独特の響きを表現したい1曲です。
まとめ・・・その時その時に合う選曲が一番!
以上、15曲のわたし流・解説とおすすめポイントでした。
バッハのシンフォニアは、全15曲きちんと経験したい曲集です。
そして、深く理解して美しく弾ければ、どの曲も素晴らしい曲です。
繰り返しになりますが、大切なことは、
- 丁寧に理解して練習すること
- あなたに合う曲や、必要のある曲は変化するし、人によって違う
レッスンでは、一人ひとりに合わせて、違う曲順で勉強しますし、舞台での選曲も変わります。
あなたの音や技術、そして目標に一番合うものを選曲してくださいね。
普段の勉強や選曲の参考にしていただければ幸いです。
〜シンフォニアに興味があるあなたへの参考記事〜
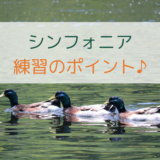 バッハのシンフォニアの譜読み・練習方法を徹底解説!フーガにも生かせるよ
バッハのシンフォニアの譜読み・練習方法を徹底解説!フーガにも生かせるよ
● インヴェンション、シンフォニアをやる意味をもう一度知っておきたいという方へ
 バッハのインヴェンションとシンフォニアは必須!難易度と進度の目安は?
バッハのインヴェンションとシンフォニアは必須!難易度と進度の目安は?
● シンフォニアをもっと素敵に弾きたい!という方へ(平均律フーガの記事ですがシンフォニアにも共通することを書いています)
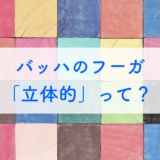 バッハの平均律、フーガを立体的に弾きたい!〜平面的に聞こえる原因を探ってみた〜
バッハの平均律、フーガを立体的に弾きたい!〜平面的に聞こえる原因を探ってみた〜
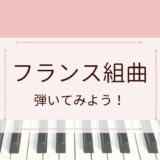 バッハのフランス組曲を弾こう!学べること・難易度・練習の進め方を解説
バッハのフランス組曲を弾こう!学べること・難易度・練習の進め方を解説





