 もも
もも
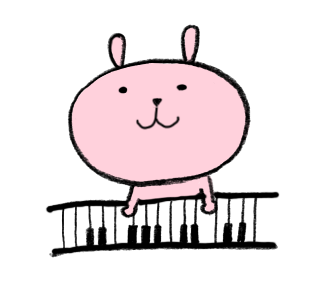 うさぎ先輩
うさぎ先輩
 さいりえ
さいりえ
演奏において、曲の構成を理解すること、そして演奏を構築することはとても大事です。
この記事では、
- 演奏の構築力って何?なぜ必要なの?
- 分析力と「どう弾きたいのか」が大事
- 作品から出発して、あなただけの演奏をつくりなおそう
- 構築力を実際の演奏に生かすには?
について書いていきます。
- 長い曲をまとめるのが苦手
- ついつい雰囲気で弾いちゃう
- 何が言いたいのかわからない、とよく言われちゃう
- 平たんな演奏になっちゃう
こんな人はぜひお読みくださいね!お役に立つことがあれば幸いです。
もくじ
構成・構築力とは?構築力のある演奏って?
ある曲を演奏するとき、その曲の構成を理解して弾くことはとても重要です。
そしてその構成をもとに、あなただけの演奏を構築していくこと。
これを、ここでは構築力と呼びたいと思います。
 もも
もも
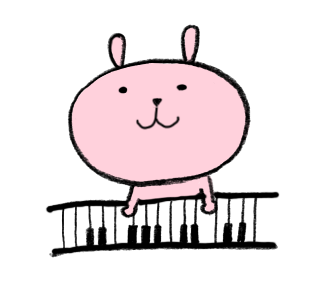 うさぎ先輩
うさぎ先輩
 さいりえ
さいりえ
構築力のある演奏とは、人があなたの演奏を聴いたとき、
- どんな曲なのかわかる演奏
- この曲、いい曲だな〜と感じられる演奏
とも言えるでしょう。
どんなに一生けん命弾いていても、
となれば魅力も半減しちゃいますよね。
もちろん現代曲や複雑な曲では、だれにでも1度でわかってもらうというのは不可能かもしれませんし、聴く人の音楽的素養なども関係してきます。
それでも、弾く人がしっかり構築した演奏と、よくわからないまま舞台に上げた演奏では大違いなんです。
曲を構築していくためには、分析と表現意志がだいじ
曲を構築していくために必要なのは、2つ。
- 分析すること
- 表現意志をもつこと
です。
構成力のためには分析力が必要、というのはなんとなくピンと来ると思うのですが、実はあなたの中に意志を持つことも同じくらい大事なんです。
順番に説明していきますね。
知識と経験を積んで、しっかり楽曲分析!
まず、曲の構成を把握するために、楽曲分析は不可欠です。
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
はじめは短くてシンプルな曲から、分析に慣れていきましょう。
そして、どんなに長く大きい曲でも、分析する習慣をつけていきます。
大事なポイントは、次のとおりです。
- さまざまな形式・様式について知っておく
- 主題の出現や変奏・展開を見つけることができる
- 調判定や和声分析ができる
これらのことに慣れていくと、分析も苦ではなくなります。
参考動画分析の方法についてくわしく書くと長くなるので、ここでは書きませんが、
「どんな感じで分析するの?」という方はこちらの動画をご覧ください↓
どう弾こう?という表現の意志
どんな曲かわかってきたら、つぎはどう演奏しよう?というあなたの意志も大事です。
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
でも、なにも奇をてらったことをする必要はありません(というか、しないでくださいね)。
主題の音型を観察したり、和声の移り変わりを分析したりすると、「こう弾こう!」というのがだんだん見えてくると思います。
- メロディの進行が美しいから、なめらかに歌いたいな
- ◯小節目で重要な和声になるから、ここに向かって深い音で…
- モチーフAとモチーフBにはこんな違いがある。それを際立たせよう
など、楽譜が教えてくれることはとても多いのです。
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
それがクラシック音楽を演奏する醍醐味でもあり、とても楽しく、奥深い時間ですよ。
分析したことを演奏に生かすには?
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
分析したことを一つの曲の演奏に生かすには、どんなことがポイントになるでしょうか?
- 部分と全体の両面から把握する
- ひとつの地図や物語のようにつくりなおす
- 音やモチーフを適切に配置していく
 さいりえ
さいりえ
部分と全体の両面から把握する
なにごとにおいてもそうかもしれませんが、演奏においても「部分と全体」というのはとても大事です。
- 弾いている自分とホール全体。
- ひとつの音と、全体の音、響き。
- 曲の一部分と、全体。
- プログラムの1曲と、コンサート全体。
曲を構築するときも同じです。
常に、細やかな一部分に敏感なあなたと、全体を大きくとらえて見つめるあなたがいるようにしましょう。
 さいりえ
さいりえ
地図や物語のように、自分の中につくりなおす
時代や曲によって、何にたとえるのがふさわしいかは変わるのですが、
たとえばこんな感じ。
- 1枚の地図のように
- ひとりの人間の物語のように
- ひとつの大きな建造物のように
- 1枚の絵画のように
- 1点を切り取った風景のように(時間は流れているが視点は同じ)
 さいりえ
さいりえ
 さいりえ
さいりえ
など、自分なりに1曲を構築します。
音やモチーフを適切に配置していく
上記のように、自分の中で楽曲を再構築できれば、演奏イメージはかなり具体的に浮かんでくると思います。
ただ、イメージがあっても
- ついついドカンと弾いてしまう
- 同じ音質を並べてしまう
- 聴かずに必死で「弾いて」しまう
と、あなたの中で構築された音楽が人に伝わりません。
あなたのイメージにそって、音を適切に出していく必要がありますよね。
そのために大事なことは、あまりにも多いのでここでは書ききれませんが
- 声部間、和声のバランス
- 音の響きの多彩さ
- クリアな発音
- その場に応じたリズム感
- 呼吸、時間の使い方のメリハリ
- あらゆる面で、表現の引き出しの多さ
などがあります。
 さいりえ
さいりえ
一生やっていくことです。少しずつでも前進していきたいですね!
まとめ
この記事では、演奏する面でとても大切な「構築力」について書きました。
要点をまとめますね。
- 構築力があれば、曲の魅力がもっと伝わる!
- 構築のためには、分析力とあなたの意思が必要
- 演奏のために、曲を分析して再創造しよう
- 終わりはない!一歩一歩、理想の演奏をめざそう
最近はTwitterのサブアカウント(@pianoplusmemo)で、このようなことをつぶやいています。
🔸音楽の構成を演奏に生かすには?
和声やモチーフの展開など、楽譜のあらゆる情報から分析することが基本だけど、理解しただけでは演奏に生きないことも。
分析に加えて、
✔︎地図や物語として、自分の中に作りなおす
✔︎部分と全体の両面から把握する
✔︎音やモチーフを適切に配置していく
— ぴあのぷらすメモ (@pianoplusmemo) 2019年6月8日
🔸わけがわからないと思って弾いている部分は、聴くひともわからない
・わけがわからない
・どう弾けばいいのかわからない
・弾くのに必死
・とにかくガムシャラに音を出す!…こんな部分は、聴く人にはますますわからない。
どんな曲かわかる、伝わるように弾くというのは、意外とむずかしい。
— ぴあのぷらすメモ (@pianoplusmemo) 2019年6月3日
🔸ややこしいところほど、和声を感じる!
楽譜が複雑な部分ほど、そこにある和声を感じ取って弾く。
いったん立ち止まって、縦の響きに耳をすませる。
まずは一箇所だけでもいい。
バンバンバーンと無意識に音を出していた部分に、色を感じる。作曲家は、その先のものを求めているはず。
— ぴあのぷらすメモ (@pianoplusmemo) 2019年6月3日
おもしろそうだなと思われた方はフォローお願いします!
あなたの演奏の役に立ちますように。
関連記事
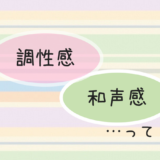 調性感・和声感のある演奏に必要なこと
調性感・和声感のある演奏に必要なこと
 構成力・和声感のある演奏って?生徒さんからの質問コーナー
構成力・和声感のある演奏って?生徒さんからの質問コーナー
参考動画
「どんな感じで分析するの?」という方はこちらの動画をご覧ください↓




