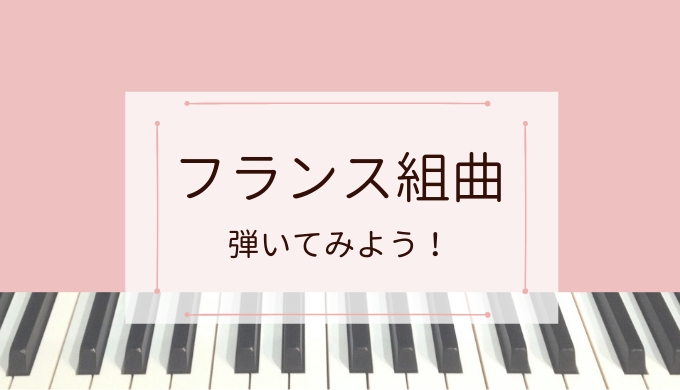バッハのフランス組曲、
小学校3年生のとき、音楽教室でお友達が弾いていて素敵だったのを今でも覚えています(上手だったなぁ…)。
ぜんぶで6曲ありますが、どれも違う魅力があって大好きです。
この記事では、
- 小学生から大人まで、比較的気軽に弾ける
- たくさん学べることがある
- 芸術作品として素晴らしい!
そんなフランス組曲をぜひ弾いてほしい理由を書いていきます。
もくじ
インヴェンションやシンフォニアだけでなく、フランス組曲を弾こう!
ピアノを習っていると、バッハを弾くのはこの流れが大きな柱になりますよね。
プレインベンション(など)
↓
インベンション
↓
シンフォニア
↓
平均律
※この流れは、多声音楽の経験・勉強として、とても重要です。
進度やスケジュール的に、シンフォニアや平均律をとにかく吸収して進めていかないといけない状況だとフランス組曲を経験できずに進学してしまうこともあり、ちょっと残念です。
でも、ぜひフランス組曲やパルティータなどの古典組曲は経験しておいたほうが良いです!(キッパリ)
フランス組曲で学べるたくさんのこと
フランス組曲では、たくさんのことを学び経験できます。
- 舞曲それぞれの特徴、リズム感、雰囲気
- カッチリした多声音楽とはまた違う様式
- 2部形式の音楽のとらえ方
- チェンバロや踊りのステップを意識した、独特の軽やかな音色
- 組曲それぞれの統一感と違いを理解して、一つの組曲としてまとめて弾くこと
- もちろん、多声作品としても学べることは多い
なんといっても、アルマンドやクーラント、サラバンド…など各舞曲の特徴のちがいや様式感を経験できることが一番ですね。
各舞曲に関しては、こちらの記事もお読みください。
 《作品メモ》古典組曲とは?J.S.バッハ 「パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830」
《作品メモ》古典組曲とは?J.S.バッハ 「パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830」
フランス組曲の経験はどんなことに生かせるの?
では、フランス組曲を経験することで、どんなことに生かせるんでしょうか?
平均律の演奏に役立つ!
平均律のプレリュード(前奏曲)、フーガにはいろんな様式のものがあります。
- 教会合唱のような曲
- トッカータふうの動きが多い曲
- 器楽合奏ふうの曲
- 舞曲ふうの曲
とくに舞曲ふうの曲で、フランス組曲を経験していれば、ふさわしい表現を見つけるのに役立ちます。
また、「いかにも舞曲」ではなくても、平均律ではさまざまな拍子が登場しますので、自然で心地よい拍子感やリズム感のために、表現の引き出しを増やしておいて損はありません。
パルティータやイギリス組曲など、さらに大きな組曲に取り組みやすい
パルティータやイギリス組曲は、フランス組曲のお兄さん、お姉さん的存在。
全組曲の前に、長くて大きな前奏曲(パルティータでは名称がちがいますが前奏曲的性質のもの)が付け加えられ、1曲ずつが長く難易度も高いです。
たとえば大学生以上になってイギリス組曲を弾こう!というときに、フランス組曲を1曲もやったことがないとちょっと辛いです。
体や感覚で覚えていると取り組みやすいですね。
(…と書いていたら、今年の学生音楽コンクールでは中学生の部にイギリス組曲が出ているんですね!かなりハイレベルだと思います)
バッハ以外の作品にも広く役立つ!
古典組曲をベースに作られた曲は、古典・ロマン派・近現代以降にもたくさんあります。
- メヌエット
- ガヴォット
- サラバンド
- ジーグ風 など・・・
グリーグ・ドビュッシー、ラヴェル、プロコフィエフ、たくさんの作曲家の作品があります。
知っておくと表現の幅が広がりますね。
つい最近、シューマンのアヴェッグ変奏曲のレッスンをしていたのですが、第2変奏のはじめに「クーラント風に」という指示がありました。
バッハのクーラントとはずいぶんイメージが変わりますが、知っているのと知らないのとでは違いますよね。
どの時代でも、バッハやバロック音楽への尊敬や憧れを持っていた作曲家が多いので、原点回帰・古典回帰の意味で古典舞曲の様式を取り入れて曲を書いたのでしょう。
ということは、演奏するわたしたちも、それらに触れ、学んでおく必要は大いにあると思いませんか?
フランス組曲の難易度や練習の進め方
フランス組曲の難易度は?
技術的にはインヴェンションとシンフォニアの間くらいの曲が多いですね。
インヴェンションを一通り弾き、シンフォニアを3〜4曲弾いたくらいのタイミングで、フランス組曲をレッスンメニューに加えることが多いです。
メヌエットなどはインヴェンションよりも譜読みしやすく弾きやすいので、まだポリフォニーに慣れていない人でもとっつきやすいと思います。
逆に、端正に多声を弾き分けて美しく弾くにはシンフォニアよりも難しいんじゃないか・・・という曲もあります。
耳や手のつかい方、リズムのとり方などがちがうので、「わたしはシンフォニアのほうが得意」「フランス組曲のほうがしっくりくる」など、得手不得手もあるかもしれませんね。
練習の進め方
つぎの方法があります。
- 1曲または数曲抜粋して練習する
- 1〜6番までのいずれかを選び、アルマンド・クーラント・サラバンド・ジーグなど主要な曲をやる
- 1〜6番までのいずれかを順に弾き、さいごに全曲通して弾く
アルマンドやクーラント1曲だけなら、インヴェンション1曲程度の難易度のものも多いです。
ほかの曲に忙しいときは、機会をつくってぜひ数曲だけでもやってみてください。
フランス組曲のために2〜3ヶ月ほど時間をとれる場合は、少しずつ進めていって、最後はぜひ1曲通して弾いてみてくださいね。
立派なリサイタルプログラムにもなりますし、達成感がありますよ。
まとめと参考楽譜、映像の紹介
この記事では、バッハのフランス組曲について書きました。
楽譜ですが、主につぎの3版を使っています。
参考までに、わたしのパルティータの演奏動画です。
よろしければご視聴ください!
フランス組曲もどれか撮りたいですね。
参考 バッハ パルティータ第6番をYoutubeで視聴するYouTubeなお、ここではバッハのフランス組曲を取り上げていますが、ほかの作曲家やもっと前の時代の組曲に触れることも良いですよね。
パーセルの組曲とか、きれいですよ!
ヘンデルの組曲第3番は、音楽高校1年生のときの前期試験課題曲でした。
むずかしかったなぁ・・・
フランス組曲の各曲をゆるく解説…という記事も時間ができたら書きたいです(いつになるやら・・・?)
〜こんな記事もあります〜
 《作品メモ》古典組曲とは?J.S.バッハ 「パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830」
《作品メモ》古典組曲とは?J.S.バッハ 「パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830」