「通し練習」。
そう、本番前に避けて通れないもの。
この記事では、通し練習の種類を
- 疑似本番を体験するための通し練習
- 自分の状態を確認するための通し練習
- 音楽的に曲をとらえて研究するための練習方法としての通し練習
の3つに分けて、
その目的・方法・ポイントを整理していきます!
 もも
もも
もくじ
擬似本番を体験するための通し練習
まずは、疑似本番を体験するための通し練習。
目的
本番のような状況に自分の身をおくことによって、次のようなものを得られます。
- 緊張感に慣れる
- イメージを高める
- 必要な体力、集中力を知る
- 緊張すると起こりやすいことについて知る、対策をとる
- 現状を知る
 本番の緊張には事前のイメトレが役に立つ!すぐできるイメージトレーニングの方法
本番の緊張には事前のイメトレが役に立つ!すぐできるイメージトレーニングの方法
 もも
もも
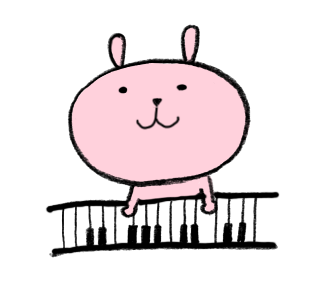 うさぎ先輩
うさぎ先輩
こんなこと、よくありませんか?
これは、ふだん弾けているというのが思い込み(=幻想)だったりします。
 さいりえ
さいりえ
そして、良いこともありますよ。
本番のときに、自分がどれだけ集中して音楽にのめり込んでいくのか?それを探ることができます。
ふだんの練習から集中するのが大事なのは言うまでもないのですが、それでも本番では特有のアドレナリンのようなものが出ますよね。
十分に準備を整えて、本番のような体験をして、その発見を練習に役立てていきます。
やり方
本番直前の場合
できるだけ本番の状況に近づけると、緊張感や気持ちを高められます。
- 心を整える
- 時間を決める
- だれかに聴いてもらう
- 録音、録画する
- ドレスや衣装を着る
- ピアノの蓋を開ける、目に入るものを減らす
- 1回きりと決めて臨む
- 配信するのもアリ
- 控え室、舞台袖、お辞儀、などから入る
本番よりもっと前に行う場合は、ここまでしなくても構いませんが、しっかり準備すればするほど「疑似本番」としての効果が得られるでしょう。
現状を確認するための通し練習
では次です。
あなたの現状を確認するための通し練習です。
わたしは譜読みの段階から、弾けないながらも最後までざーっと弾いて全体像を見たりするのですが、
いままでお話した生徒さんの中には「本番直前までほとんど通したことがない」という人もいるようです。
理由をきくと、
- まだ弾けていないから
- 弾けていないことがわかるのがこわいから
- 最後まで通せる気がしないから(想像もできないから)
などが理由のようです。
気持ちはわからなくもないですが、それでは曲の全体のイメージもつかめないし、本番のために何が必要かも直前までわかりづらいですよね。
最悪の場合、ギリギリになって間に合わないこともあるかもしれません。
そんな人は、まだ不十分でもかまわないので、一度エイッと通してみてください。できれば、暗譜で。
目的
このような成果を得ることが目的です。
- 本番でその曲を弾いているイメージがまったくわかない、という場合に、大まかなイメージを持てる
- いま自分がどのくらい弾けているのか(or 弾けていないのか)がある程度わかる
- 本番までに必要なことや時間を見極める
方法
たとえば
- いつも楽章ごとに練習しているなら、たまには全楽章通す
- まだ自信はないけど、一度暗譜で通してみる
- 弾けない部分があっても、一度テンポを上げて通してみる
注意点・ポイント
そこまで周到に準備をしなくてもよい
上の「疑似本番のための通し練習」ほどの準備はしなくても良いでしょう。
たとえば、まだ弾けていないのにドレスを着る必要もありません。
何度もやらなくてもよい
それから、何度も何度もやらなくてもいいです。
「あ〜、全楽章通すとこんな感じなのか!」と大まかにわかれば、また音楽を構築する練習に時間をつかいましょう。
通し練習は時間もかかりますし、細かいことに気づきにくいので、練習の半ばでは時間のバランスが重要です。
舞台に乗る自分をイメージする
仮に演奏が不十分でも、舞台で弾いている自分をイメージします。
すると、理想の自分と現状の自分との差がわかるはずです。
それを埋めていくのが練習の大事な要素のひとつです!
演奏を創り上げていくための通し練習
では最後に、演奏の内容のための通し練習です。
これはわたしも、けっこうやる練習です。
また、「通し練習」といっても「何が何でも通す」「ぜったい止まっちゃダメ」というわけではありません。
なんでしょうか、ひとつのマラソンコースをスタートからゴールまで、景色や地面やいろんな要素を確認しながら最後まで歩いてみる、そんな感じです。
目的
- 曲全体を見るため
- 部分間のバランスや時空の違いを確認するため
- 曲全体を演奏するための体力・集中力を知るため
- 部分的な練習とは違うものを得るため
いつやるの?
いつでも。譜読み中でも意味があるし、本番前日や当日にも、よくやります。
方法
いろんな方法でできます。
- 少しゆっくりめでもいいし、まだ弾けなくても速く弾いても良い
- 楽譜をよーーーく見ながら/暗譜の確認なら、楽譜なしでも
- 音を聴きながら(いつでも)
- 気になることがあれば止まってもいい(ただし、止まりグセがある人は「何があっても音楽を止めない」という練習を多めにするなど、臨機応変に)
ポイント
気になったことはメモしていく
通し練習をしていると、前半に思ったことを忘れたりしちゃいます。
適宜、メモしておきましょう。
部分練習と、ほどよい割合で時間配分していく
通し練習ばっかり、部分練習ばっかりではバランスが悪いですね。
部分練習も、短い部分練習や数十小節単位、など、あなたの必要な要素に合わせていろいろやってみてください。
良くない通し練習とは?
ここまで、3つの通し練習をご紹介しました。
では最後に、こんな通し練習はダメ!の紹介です。
- 考えないで通す
- 何回も通すだけ(ただし、指や頭に覚えこますなど、限定的な場面で有効なこともある)
- 目的がはっきりしないまま通す
- 通すことだけで満足してしまい、振り返りのない通し練習
 もも
もも
まとめ 通し練習
この記事では3種類の通し練習をご紹介しました。
- 疑似本番を体験するための通し練習
- 自分の状態を確認するための通し練習
- 音楽的に曲をとらえて研究するための練習方法としての通し練習
今日からの練習に生かしてみませんか?
 本番の緊張には事前のイメトレが役に立つ!すぐできるイメージトレーニングの方法
本番の緊張には事前のイメトレが役に立つ!すぐできるイメージトレーニングの方法




