「和声聴音が苦手です。どうすれば、とれるようになりますか?」というご相談をときどき受けます。。
苦手意識が強くなるとなかなか壁をこえられず、苦労することもありますよね。
ソルフェージュの試験だけでなく、ピアノの演奏にもかかわってくる大問題です。
 もも
もも
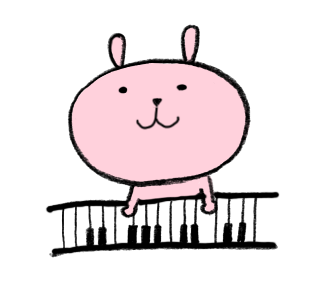 うさぎ先輩
うさぎ先輩
 さいりえ
さいりえ
そこでこの記事では、和声聴音が苦手な人のための対策を紹介します。
- あなたは和声聴音の何が苦手?
- ふだんからできる!和声に敏感になるための方法
- 音楽理論、和声法を学ぼう!初級から使えるおすすめテキスト
- 実際のソルフェージュのレッスンでの具体的な進め方
これらをくわしくご紹介していきます。
和声に親しみがもてるようになれば、実際の演奏への取り組み方や音の聴き方が格段に変わるはずですので、和声聴音が苦手な方はもちろん、ピアノを演奏される方はぜひお読みくださいね。
 さいりえ
さいりえ
もくじ
和声聴音のなにが苦手?
和声聴音が苦手な人は、次のようなタイプに分かれます(複数のことも)。
あなたの苦手ポイントはありますか?
- 低音が聞こえづらい
- 内声が聞こえづらい
- 臨時記号が出てくると途端にわからなくなる
- 各声部が動くとわからなくなる
 さいりえ
さいりえ
対策ですが、ふだんから音楽に接しながら基本的な底力をアップさせつつ、苦手な項目は集中してトレーニングすることが大事です。
ふだんからできる対策
和声聴音は、ソルフェージュのお勉強の時間だけに突然あらわれるものではありません。
ふだんあなたが接している音楽、あなたが弾くピアノの中に、いつもあるんですよね。
ふだんから、和声に対して耳を使って感じていくことが一番の近道です。
歌う
- ふだん弾いている曲の一部の声部を歌う
- ピアノである音を弾いて、音程をとって歌う
- 合唱や重唱など、人とあわせて歌う
ふだん弾いている曲のいろいろな声部を歌ってみるのが、いちばん取り組みやすいです。
音程をとるのがむずかしければ、ピアノで音をとりながらでもかまいません。
けっこうむずかしくないですか?
ふだん、いかに聴けていないか?に気づくこともあります。
「ド〜ミ」「ド〜ラ」など、音程を歌うのも良い練習です。
また、合唱で歌う機会があれば、耳のためにもとても良い経験になります。
弾く
賛美歌、コラールは4声でできていることが多いので、実際に弾いてみると良いです。
- 和声の自然な進行に慣れる、覚える(理論・手・耳)
- 実際に弾くことで、各音への意識を高める
- 4声の響き、重なりに慣れる(耳)
よく聴きながら&歌いながら弾くことで、あいまいな部分が少なくなり、定着しやすくなります。
聴く
とにかく、これまで以上に意識して、耳をひらいて聴きましょう。
- 自分の音を聴く
- 賛美歌、コラールを聴く
- 合唱を聴く
- 弦楽四重奏を聴く
まずは自分の音を聴くこと。
伸びている音を聴くこと。
音の重なりを聴くこと。
音のへだたりを聴くこと。ですね。
合唱曲や弦楽四重奏曲、オーケストラなどをたくさん聴くのも良いですね。
さらに、声を出して歌ったり楽譜に書いたりして「耳↔目↔自分の声」を行き来するように繰り返すと、とても勉強になります。
音楽理論を勉強して、しっかり裏付けする
和声聴音は、ただ聴こえてきた音を耳で聴いて書くだけではありません。
音楽理論や和声法を知っていると、格段に音を取りやすくなります。
また聴こえづらい部分も、「こう進んでいるから、ここはこの音かな…?」と、知識からもある程度補えるようになります。
- 4声のそれぞれの音域、配置の特徴
- 各声の進行の特徴(内声は跳躍が少なめ、など)
- 和音の機能
- 和音記号
- 頻出する形(終止形など)
- 特定の和音進行の特徴(限定的な音の進行など)
- 調性や転調の知識
などを勉強していきましょう!
総合的な音楽理論の基礎を身につける
楽典の知識については、こちらの記事でも書いています。
- 和音記号
- 和音の展開形について
- 調判定
などについて、シンプルに学べます。
 【後編】ピアニストのための楽典学習!「黄色い本」の重要ポイントをチェック!
【後編】ピアニストのための楽典学習!「黄色い本」の重要ポイントをチェック!
和声法を学ぶ(はじめは入り口だけでもOK!)
4声の和声のルールや実施など、学んでみると、和声に少しずつ強くなれます!
(すみません、初級の方におすすめのテキストがわかりません…良いのが見つかったらまたシェアします!)
以下は、1冊目としては難しいかもしれませんがご紹介しますね。
学生時代はこちらの本を使っていました。
現在の東京芸大では、こちらのテキストを使っているそうです。
楽譜を分析してみる
聴き取った楽譜や、手近にある曲の楽譜から、分析(アナリーゼ)してみます。
こちらの本は、オンラインレッスンでアナリーゼを指導させていただいた方が使われていたのですが、とてもわかりやすかったです。
基本的なことから発展的な内容までを網羅していて、1冊あれば大まかな分析には困らないと思います。
ソルフェージュ対策・和声聴音の進め方のポイント
ではここまでで、基礎的な和声力を少しずつ積み上げられたら、つぎはソルフェージュのときの具体的な対策や進め方をご紹介します。
指導者の方も、ご参考になりましたら取り入れていただければと思います。
単発の和音から
4声体がとれない、苦手という場合、単発の和音から聴き取る練習をします。
2つの重音から3つ、4つ、5、6…と音を増やしていきますが、4つくらい聴こえればまずはOKです。
いろんなパターンの和音を聴き取ります。
- ピアノの鍵盤上で、片手で弾ける狭い音程/両手を広げて弾く広い音程
- 基本形/展開形
- 各音1つずつ(G-D-H-F など)/音を重複させたもの(例:C-G-C-E など)
- 機能的な和音/不協和音
- すぐに口頭で答える/何度か、聴き取りながら書く/何度か聴いて、暗譜で書く
慣れてきたら、単発ではなく連結の和音にします。(ポーン、ポーンと2つの和音を聴いてから、2つまとめて答える)
このときも、和声的に進行している和音にしたり、無関係な和音を並べたりしていきます。
4声が聴きづらい場合は2声、3声から
多声が横に流れるのを聴きづらい場合は、2声、3声などの曲で、横のラインを聴く練習をします。
このテキストは有名ですが、2声や3声の問題も豊富です。
3声の問題も、【高音域2声+低音域1声】と、【高音域1声+低音域2声】があります。得意不得意によって問題を選ぶと良いでしょう。
また応用編として、「4声の曲を、先に3声だけ弾いてもらって書き取る→3声が完全に書けたら、4声で弾いてもらって残りの1声を書き取る」という方法もあります。
残りの3声が完成した状態であれば、苦手な声部がすこし聴こえやすくなるようです。
和音の度数や機能だけを答える
和音の音すべてを聴き取らなくても、その和音の役割だけを答える、という方法があります。
物理的に正確に音を聴き取ることよりも、音楽的な意味を聴く・考えることにつながります。
つまり音楽的な耳が養えますし、演奏にも役立ちます。
- 和音の度数(Ⅰ度、Ⅴ度など)
- 機能(トニック、ドミナントなど)
- 種類(長三和音、減三和音など)
- 終止の種類(半終止、完全終止など)
- 調性(◯◯調)
先生がいる場合、弾き方を変えてもらう
先生や家族など、ほかの人が問題を弾いてくれる場合、あなたの苦手な部分にあわせて弾き方を変えてもらいましょう。
- 苦手な声部を強く弾いてもらう
- ゆっくり弾いてもらう
- 一部分だけを繰り返し弾いてもらう
- 間違えやすいパターンを比較して弾いてもらう
- 音色を変えてもらう(ピアノ1台ではちょっとわかりにくいけど)
など、マンツーマンならではの指導が受けられると有意義ですよね。
苦手な要素だけを繰り返し学習する
和声がまったく取れない…という段階は別ですが、ある程度聴き取れる人の場合、「これが苦手」と決まっていることもあります。
- 内声が跳躍するとわからなくなる
- 借用和音が出てくると、わからなくなる
- 音はわかるけど、臨時記号を間違える(異名同音の間違い。音楽的意味を理解できていない場合に起こりやすい)
- 特定の進行のルールを覚えられていない
…のように、特定の苦手分野がある場合、それに徹底して取り組みましょう。
- 同じ問題を繰り返す
- 要素は同じだけど違う曲を解く(自分で作ってみるのもOK)
- 移調してもできるか、やってみる
- もう一度ルールを確認する
など、具体的に取り組みます。
復習する
これが大事です!
その日のソルフェージュレッスンや学習が終わったら、うまく聴き取れなかった部分をかならず復習しましょう。
ピアノとちがって、ソルフェージュは1週間に1回のレッスンを受けたら終わり…となりやすいですが、それではなかなか苦手を克服できません。
- 聴き取れなかった声部を歌ってみる、
- 家で弾いてみる
- 移調して弾いてみる
など、いろいろな角度から接してみましょう。
同じ課題を繰り返す。覚えてしまってもOK!
あまり聴き取れなかった課題は、何度か繰り返して取り組むのもアリです。
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
何度も聴いて書いてマルつけをしているうちに、たしかに覚えてしまいます。
でも、学習しながら耳が慣れていくことで、聴き方が変わってきます。
- 音をひとつずつ聴く
- 横の流れが聴こえる
- 縦の響きの聴こえ方が変わる(その音がそこにある、とわかると、聴きやすくなる)
- 和音の役割を感じられる(知っていてもOK)
- 音楽の方向性が見えてくる
など、いろんな聴こえ方が生まれてきます。
答えを知っていてもかまわないんです。
ある課題を、あらゆる角度からバッチリ聴けて認識できるようになれば、新しい課題の聴きやすさも少しずつ変わってきます。
まとめ〜あらゆる角度から音楽基礎力をつけ、和声聴音にも演奏にも役立てよう!〜
この記事では、和声聴音が苦手な人に向けて具体的な対策をご紹介しました。
ここまでお読みくださった方はお気づきかもしれませんが、これらは何も
聴音の試験で高得点を取るため だけの対策ではありません。
- 音楽の持つ力や役割、方向性がわかる
- 音楽を作っている、ひとつひとつの音を大事に感じられる
- 演奏するときに、どのように音を組み立てれば良いのかがわかる
- 自分や他人の音を正確に、そして音楽的に聴く
など、演奏したり音楽に接したりする上で大切なことをたくさん学べます。
和声聴音への苦手意識をなくし、和声の美しさや奥深さを存分に楽しめますように!










