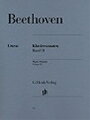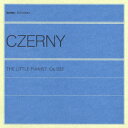こんにちは、さいりえです。
先日、「音高受験を考えているので副科ピアノを教えてほしい」とご相談を受けました。
あいにく副科の方の継続レッスンは承れない状況なのですが、現在わたしは音楽高校で副科ピアノのレッスンも行っている身なので、なにかお役に立てることがあればということで
一度ご相談と単発レッスンにお越しいただきました。
そこでこの記事では
音楽大学、音楽高校を(ピアノ科以外で)受験したい人に必須の「副科ピアノ」と、その準備について
を記事にしようと思います。
- なぜ副科ピアノが受験科目にあるのか、なぜ必要なのか?
- 入試までにどのくらい弾けていたらいいの?
- これから副科ピアノの対策をしたい人におすすめの曲やテキスト(レベル別)
をご紹介していきます。
もくじ
音大受験・音高受験に必須の副科ピアノ。なぜ必要なの?
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
副科ピアノ。
得意な人や好きな人はいいですが、ピアノが苦手な人にとっては「なんでやらないとあかんの?」「イヤだなぁ・・・」と思っちゃいますよね。
でも、ピアノは自分の専攻にかかわらず、経験することでたくさんの良いことがあります!
たとえばこんなこと。
- 単旋律の楽器や歌(ソロ)では体験できない【和声や複数の音・声部の組み立て、響き、聴き方】を経験する
- ピアノを通して、さまざまな音楽様式や歴史を学べる(各楽器でも学べますが、体系的に学びやすいです)
- 結果、専攻楽器への取り組み方も変わる
ピアノは複数の音や声部を出しやすいですし、あらゆる時代や様式・難易度の曲が豊富ですので、クラシック音楽の基礎や歴史を学ぶにも、とても意義ある楽器です。
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
将来に向けても、ピアノが弾けると役立ちます。
- 伴奏してもらったり室内楽をしたりする場合、ピアノについてある程度知識やイメージがあるほうが良い
- 将来、楽器を教えたりするときに多少はピアノを弾けたほうがいい(学校や保育園の先生になるなら必須)
ほかにも、副科のピアノの生徒さんを教えていて、こんなこともあります。
- 専攻楽器のレッスンを、たまにピアノの先生に受けてみる
- 専攻楽器についての悩みを、ピアノの先生に相談してみる
わたしは各楽器の知識はもちろん不十分ですが、それでも彼らに、音楽家として、指導者としてアドバイスできることは見つかるものです。
同じ楽器じゃないからこそ、ピアニスト的視点だからこそ言えることもあったりします。
セカンドオピニオン的なこともあるかもしれません。
参考 複数の先生にレッスンを受けるってどうなの?メリット・デメリット・注意点 | ピアニスト崔理英 オフィシャルサイト&ブログ取得できませんでした もも
もも
そんなわけで、弦楽器や管楽器、また声楽や作曲、指揮…と、あらゆる楽器や専攻を志す人に、
というのが、音楽大学・音楽高校の受験科目に副科ピアノが入っている、大きな理由なのです。
音大・音高受験までに必要なレベル、めざすこと
では次に、音楽大学や音楽高校を受験するために必要なレベルや目標を書いていきます。
まずは大前提として、
- 試験に合格する
というのがありますね(もちろん、最終目標ではありません)。
そのためには
ピアノを両手である程度弾けるようになる
くらいのレベルが必要になります。
ある程度というのは学校によってさまざまで、
- ソナチネ〜やさしいソナタ程度
- ツェルニーの30の練習曲程度
- バッハのインヴェンション程度
- ハノンのスケール(No.39)の複数の調
くらいが多いようです。
各大学・高校の過去の入試課題については、以下の記事を参考になさってください。
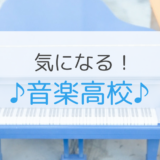 [2021年版]音楽高校の受験方法・課題曲・レベルの調べ方
[2021年版]音楽高校の受験方法・課題曲・レベルの調べ方
また、曲のレベルだけでなく、
- ピアノを弾く基本的な姿勢や奏法
- 大譜表を読むこと
- 複数の音、声部、和声を聴き、感じること
- 人前でピアノを弾き無事に演奏し終えるという経験(試験は暗譜)
が最低限必要です。
とくにこれまでの経験が少ない場合は、「人前で無事に弾く」ということが一番大変かもしれません!
自分の楽器で本番を経験しているとは思うのですが、
- 慣れない楽器
- 両手を別々に動かす
- 単旋律とは違い、複数の声部を覚えることに慣れていない
などの場合、頭が真っ白になっちゃいました!という人もいます。
 さいりえ
さいりえ
ですが、これまでの楽器経験と同じで、しっかりと準備のステップを踏み、経験を積むことで少しずつ慣れていきますので、安心してくださいね。
そのためには、
- 順序立てて学び、経験を積むこと
- できるだけ早く始めること
が大事です。
受験直前は、どうしても専攻楽器の練習に時間を費やしますし、副科ピアノの練習時間もそんなに多くはとれないと思います。
それに、付け焼き刃ではなかなかうまくいかないのが、ピアノという楽器です。
この記事を読んでいる方で、副科ピアノの受験について不安だなぁと思われたら、少しずつでも、いまから始めていきましょう。
副科ピアノの受験対策や日々の学習におすすめの教本や曲集〈レベル別〉
では、副科ピアノを受験に向けて(それ以外でも)やっていこう!と思われる方に、おすすめの教本や曲集をレベル別にご紹介していきます。
ピアノ経験者の人は、楽しく&本格的に、いろんな時代様式の曲で経験を深めよう
ピアノ以外の楽器で音大や音高に進学する人の中には、【もともと小さいころからピアノを習っていた】と言う人も一定数おられます。
発表会やコンクールにも何度も出ていたり、中にはピアノ科顔負けの演奏をされる方もおられます!
そんな方は、基礎の再確認をしながら
- 演奏技術
- 音楽の基礎力
- 表現力
をまんべんなく上げましょう。
- ハノンやツェルニー、さらに高度なエチュード
- バッハの多声作品や
- 古典派ソナタ
- ショパンやシューマンなど、ロマン派の作品
- フランス音楽
- その他の近現代曲
- 自分が専攻で弾いている曲に関連する作曲家や時代の曲にもチャレンジ
など、いろんな角度から取り組むと良いでしょう。
いくつかの楽譜を紹介します。
バッハのフランス組曲や平均律
J.S.バッハのフランス組曲。
初級〜中級であればどうしてもインヴェンションなどをみっちりとなりますが、そういう段階を少し越えた方はぜひやってみてください。
バッハの平均律クラヴィーア曲集(プレリュードとフーガ)。バッハが好きならぜひ。
ベートーヴェンのピアノソナタ
あこがれのベートーヴェンのソナタ。わりと弾ける副科の生徒さんは、数曲取り組んでいます。
とくに作曲・指揮・楽理・弦・管打楽器の人にとっては、交響曲に通じるソナタを弾いてみるという経験はとても大事です。
第1番・5番・10番などの取り組みやすいものから、悲愴や月光、テレーゼなど憧れの曲にエイッとチャレンジできるのも副科の人の特権かもしれません?
(※上に挙げたうち、5曲は第1巻に、テレーゼだけは第2巻に入っています)
ロマン派の作品(例:シューマン)
ロマン派の作品もたくさん体験して、「歌う心や表情」を体感していきたいですよね。
声楽の人は、シューベルトやシューマンを弾くのも良いですね。
シューマンの「幻想小曲集」。『1.夕べに』は美しく、『2.飛翔』は人気の1曲です。全8曲。
ブラームスのラプソディ。ブラームスの交響曲が好き、という管楽器の生徒さんにおすすめしたことがあります。
近現代の作品(例:ラヴェル)
ラヴェルの「ソナチネ」や「鏡」。
鏡の『2.悲しい鳥たち』は本格的に取り組むにはとても難しい曲ですが、読譜して音を出すのはそこまで難しくないです。フランス音楽の響きの美しさを体感できます。
いままで副科の生徒さんが2人弾きましたが、とても世界観のある演奏をしていました。
ピアノ科の人ほど指は動かなくても、音楽的な感性を持っている人はたくさんいます。いろんな曲に触れてほしいなと思います!
(ソナチネは第1巻/鏡は第2巻に入っています)
プロコフィエフのバレエ曲のピアノ編曲版(本人編曲)。
コンチェルトや交響曲などは大きな規模・形式のため、こういった性格的小品に触れるのも良い体験です。
たくさんご紹介しましたが、あくまで一例です。
 さいりえ
さいりえ
ここからは、未経験の方や、ちょっとだけ習ったことはあるけど…という方向けです。
ピアノ未経験の人は、大譜表や両手の指を動かすことに慣れていこう
音大や音高を受けたいけど、ピアノはほとんど弾いたことがない・・・という人もおられると思います。
- 合唱団で歌を歌っていて、声楽科をめざしたい
- 中学や高校で吹奏楽部に入って、その楽器で音大に行きたい
という人などで、それまで楽器の経験がなかった、という人が多いようです。
そんな方は、まず
- 両手の10本の指を動かすことに慣れる
- 2つ以上の旋律や和音を聴く・歌うことに慣れる
- 大譜表を読むことに慣れる
- 人前でピアノを弾くことに慣れる(まずは先生や家族の前でOK)
ということから、コツコツはじめていましょう。
未経験とはいえ、歌や楽器をやっているということは
- 楽譜を読める
- ある程度音楽基礎力がある(同じテンポで演奏できる、何調・何拍子かわかる、など)
はずです。
完全な初心者と違い、上達スピードが速いと思いますので、最初は大変かもしれませんが、頑張っていきましょう!
教材えらびのポイントは、次のようなことです。
- まずは基本的な曲・やさしい曲から始める
- 得手不得手があるので、その後の進度は様子を見ながら
- 子ども向け教材がちょっとイヤなら、大人初心者向けの本もたくさんある
いくつかご紹介していきます。
初級者向けハノン
いきなり本編のハノンを買うと音符も小さいし、いかにも「ピアノのお勉強!」という感じ。
かといって「中学生や高校生で子どものイラスト向けもちょっとなぁ・・・」と思う人にぴったりです。
各社こどものハノンと同じような内容ですが、きれいで大人っぽいデザインです。
2オクターブのスケール(本編は4オクターブで難易度が高い)や、ハノンNo.1〜の内容も短く、リズム変奏も提案されています。
音符の大きさもほどよく大きいので、読みやすいです。
 ハノン・スケールとアルペジオの使い方。ただの指練習じゃない!
ハノン・スケールとアルペジオの使い方。ただの指練習じゃない!
ツェルニーのリトルピアニスト
ツェルニーのリトルピアニストは、始めはすごく易しいのですが、ツェルニー100番などと比べて、進度が早いです。
ヴァイオリン経験者、音楽教室に通っている人などのレッスンで使ったら、スイスイ進んでちょうど良かったです。
バッハの小品集
メヌエットや小さいプレリュードなど、ポリフォニーの基礎となる曲が入っています。
上達の早い人なら、これが終わればインヴェンションに入ることもできます。
ブルグミュラーの練習曲
子ども向けと思われるブルグミュラーですが、ほんとうにたくさんの大事な要素が詰まっています!
音楽経験者であれば(ピアノ未経験でも)、ゆっくり譜読みしていけば弾ける曲もあると思います。
むずかしすぎるようならもっと短い曲から、また、スラスラ進めるようならシューマンのユーゲントアルバムやショパンのワルツなどにだんだん移行しても良いですね。
(ここでは特定の出版社の楽譜をご紹介していますが、各社版あります)
副科ピアノのレッスンは、しばらくやってみないと進度の予測がつかないこともあります。
ずっと苦手…という人もいれば、すごいスピードでメキメキ上達する人もいます。
上達の速度や質の高さのためには、音楽基礎力を持っているかどうかも重要です。
音楽理論やソルフェージュの学習も、かならず並行して進めていきましょう。
 音楽高校を受験したい![2] 今すぐ楽典&ソルフェージュ!おすすめテキストと問題集
音楽高校を受験したい![2] 今すぐ楽典&ソルフェージュ!おすすめテキストと問題集
 ピアノを弾くなら知っておきたい楽典の基礎。音高・音大受験に必須の「黄色い本」を解説![前編]
ピアノを弾くなら知っておきたい楽典の基礎。音高・音大受験に必須の「黄色い本」を解説![前編]
そのほか、副科ピアノの音大・音高受験対策についてよくある質問集
ここからは、よくあるご質問とそれに関するお答えをご紹介します。
一部、ここまで述べたことと重複するかもしれませんがご了承ください。
音大・音高に入るには、副科でどのくらいの曲が弾ければいいですか?
最低限は音高ならソナチネ、音大ならスケールと、インヴェンションやソナチネ〜ソナタレベルです。志望校の課題曲も確認してください。
入試曲だけ必死でやれば受かりますか?
試験曲だけでも必死で練習すれば、なんとかなることもあるかもしれません。しかし入学後、そしてその先のことを考えれば、しっかり基礎から積み上げたほうが絶対に良いです。
副科ピアノの準備は独学でできますか?
曲を弾ける・弾けないだけでなく、基本的な奏法や、広い音楽的視野をもって学ぶ必要がありますので、副科であっても個人レッスンをきちんと受けることをオススメします。
どのくらい練習すればいいですか?毎日弾かなきゃダメですか?
できれば毎日弾くことが理想です。15〜30分でもかまいません。でも、あなたの楽器の演奏会やコンクール直前など、どうしても厳しいこともあると思います。そんなときは先生にご相談して、課題の量に少しメリハリをつけてもらったら良いかと思います。
副科ピアノが苦手です。楽譜を見てもわけがわからないし、全然弾けません。
あなたのレベルに合った曲からでかまいません。そして、ソルフェージュ、楽典を学びましょう。短い曲でも「意味を理解して」弾けるようになると、少しずつ接しやすくなると思います。
(指導者目線)ピアノのレッスンと、副科ピアノのレッスンで違うことはありますか?
(わたしの場合)副科の人には、ピアノ上達という目的だけではなく、【専攻楽器の一助となるためのピアノレッスン】としてレッスンしています。ですので、目標の立て方や選曲の方針も異なることがあります。
ほかご質問があればお寄せください。こちらのコーナーに追記していきます。
まとめ〜ピアノを通して、あなたの楽器演奏力もさらに深まるはず。受験対策は今すぐスタート!〜
この記事では、副科ピアノが必要な理由や、音大・音高受験の対策についてご紹介しました。
目の前のことに精一杯だと、「なんでピアノなんかやらなきゃいけないの?」と思うこともあるかもしれませんが、長い人生の中できっと役立つはずです!
たくさんのことを一気にやる必要はないので、ぜひ今から、ちょっとずつでも始めてみてください。
冒頭に書いたとおり、レッスンは行っていないのですが、単発の面談やご相談は承っています。
LINEからご相談ください(簡単な内容でしたら無料です/継続的な内容・こみいった内容は有料となる可能性があります)。
 音楽高校を受験したい![2] 今すぐ楽典&ソルフェージュ!おすすめテキストと問題集
音楽高校を受験したい![2] 今すぐ楽典&ソルフェージュ!おすすめテキストと問題集
 ピアノを弾くなら知っておきたい楽典の基礎。音高・音大受験に必須の「黄色い本」を解説![前編]
ピアノを弾くなら知っておきたい楽典の基礎。音高・音大受験に必須の「黄色い本」を解説![前編]
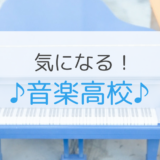 [2021年版]音楽高校の受験方法・課題曲・レベルの調べ方
[2021年版]音楽高校の受験方法・課題曲・レベルの調べ方