「コンクールの結果に納得できない」
という声をきくことがあります。
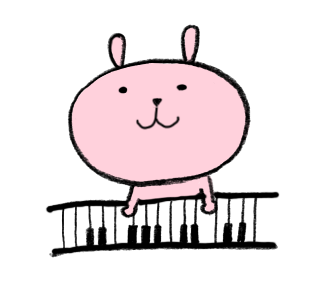 うさぎ先輩
うさぎ先輩
 もも
もも
 さいりえ
さいりえ
コンクールの結果って、単純なものではないんですよね。
わたしもこれまで、「なんで落ちたんだろう」と思うこともありましたし、逆に「なんであの演奏で受かったんだろう」と思うこともありました。
この記事では、いくつかのコンクールで審査員を務めた経験をもとに、
- コンクールの点数、結果について思うこと
- 結果より大事なことってある?
- コンクールってあなたにとってどんな場所?
について書いていきます。
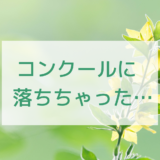 コンクールで落ちた・賞をもらえなくて落ち込むときの対処法
コンクールで落ちた・賞をもらえなくて落ち込むときの対処法
もくじ
審査員の経験から語る、点数と結果が意味するものとは
わたしは今まで、いくつかのコンクールで審査を務めたことがあり、勤務している音楽高校でも、試験のたびに点数をつけています。
コンクールでは、各演奏者に点数をつけ、最後に審査員の点をまとめた結果が出るのですが、
ほんとうに 単純じゃないな と思います。
コンクール審査の主要な方式
はじめに、よくあるコンクールの審査方法について簡単に説明しておきますね。
コンクールによって評価方法はそれぞれですが、多いのは各審査員が数字で点数をつけて、平均点や合計点を出すというもの。
そして細かいルールも
- 上下点カットする/しない
- 自分の門下生の点数をつける/つけない
- 同点の場合のルール
など、いろいろあります。
 さいりえ
さいりえ
わたしが点数と結果について「単純じゃない」と感じるのは、2つの点において。
- 自分が点数をつけることに対して
- 全員の審査を終え、審査結果に対して
完璧にスッキリした!とは思えないこともあります。
点数をつけるってむずかしい!いつも悩みながらつけている
まず、審査員として、ひとの演奏に点数をつけるというのは、とても大変なことです。
音楽という形のならないものに、数字というもっともハッキリしたラベルを貼らなければならない、というのはとてもむずかしい。
- 音楽的な方向性や歌い方がとても素敵!でもほんの少し物足りない気がする
- すごく達者だけど、なんだかこの曲と合ってない
- 全体的にちょっと粗いけど、すごく生き生きしててイイ!
- すごくいいけど、ちょっと間に合わなかったのかな…
こういう演奏を、点数という一つのモノサシで並べろと言われるようなものですから、そりゃもう・・・むずかしいですよね。
だから、同じ点数だとしても、意味がまったくちがうことも多いんですよね。
 さいりえ
さいりえ
耳と脳と思考をフル回転で使います。
もし参加者の方から、「なぜわたしにこの点数をつけたのですか?」ときかれたら、ちゃんと自分の基準を説明できるつもりで、つけています(納得してもらえるかどうかはわかりませんが)。
 さいりえ
さいりえ
 コンクールになるとこわい・緊張するという人へ~審査員はどんなことを考えている?~
コンクールになるとこわい・緊張するという人へ~審査員はどんなことを考えている?~
結果を見て、「人それぞれ」を感じる
そして、なんとか自分なりに納得いく評価をつけた後。
審査員全員の点数評価を事務局の方がまとめ、平均点もしくは合計点が出ます。
- 自分はとても良い点をつけたけど、周りはそうでもなかった
- 自分があと1点高く入れていたら、この人は入賞 or 通過していた
- 思ってもいなかったような人が上位に入っていた
こんなことはしょっちゅうあります。
ちなみにわたしは、
- 音楽を感じられるか
- 音色や響きが美しいか
- 「楽しみ」があるか
をとくに重視しています。
 さいりえ
さいりえ
もちろん、
- 自分が高く評価した演奏に他の人も高得点をつけていて、1位になった
- 当落線上かな・・・と思う演奏が、ちょっとしたことで結果が変わる
など、予想通りなこともありますが。
審査員もそれぞれ、ちがう価値観で審査しています。
自分とすごく似ている人、全然ちがう人もいます。
演奏は総合的に評価しますが、その中でもどちらかといえば技術重視、音色重視、
まったくちがう人生を歩んできた人が、それぞれの観点や優先順位で評価をしています。
だから、結果が変動するのは当たり前ですよね。
基本的には、結果はそれぞれの審査員の評価が平均化されたものです。
意図的な点数操作などは論外ですが、そうでなくてもコンクールの結果は移り変わりやすい、水物(みずもの)なんです。
たとえば、わたしが以前伴奏したコンクールでは審査員全員の点数が公開されていたのですが、全員の審査員が2位の点数をつけた方の平均点がいちばん高く、優勝されていました。
思うような結果が得られなかったときに、点数や結果の意味をあんまり考えても、すべてに納得することはできないと思います。
- 審査員が変われば、結果はまったく同じにはならない
- 何が理由だったのか、なんて本当にはわからない
- 点数が公開されれば多少はわかるけど、すべてを理解することはできない
- 一人ひとりちがう音楽観をもつ人間が審査していることを知っておく
- 最終的には自分が信じる道を進むしかない
結果を受け止めつつ、あなたが成長できたことや、これからやっていこうと思う課題を新たに心にとめることができれば良いのではないでしょうか?
コンクールって、どういう場所なんだろう?
では、コンクールってどんな場所なんでしょうか。
人によってちがうと思います。
- 賞を競うところ
- 誰よりもうまく弾くことを目指すところ
- 一生懸命練習したことに対して評価をもらうところ
そういう側面もたしかにあるでしょう。
でも、価値があるとわたしが思うのは、
- ギリギリまで、自分自身、自分の音楽と向き合って向上することができるところ
- 自分を応援してくれる、自分の音楽に共感してくれる人に出会える(かもしれない)ところ
ではないかと思います。
とことん向上できる場所
ふだんから目の前の音楽に真剣なつもりでいても、やはり本番というのは特別なものです。
〆切がある、本番がある・・・ということで実力以上の自分が出てくることもありますし、緊張感やプレッシャーと極限までたたかった末に見つかるものもあります。
そうやって音楽と向き合って、
- それまでにはいなかった自分を発見したり
- それまで得られなかったことを得たり
- それまでとは、音楽との向き合い方が変わったり
できるのが、コンクールや大きな本番での価値ではないでしょうか。
良い結果が得られれば嬉しいし、一生懸命取り組んで結果が出ないときは悔しく、空しい気持ちになるかもしれません。
でも、真剣に取り組んだ末に「得られたもの」はその人だけ、あなただけのものです。
それに自信を持って、喜んでもらいたいなと思います。
自分の音楽に共感してくれる、応援してくれる人と出会える場所
コンクールには、聴いてくれる人がいます。
審査員だけでなく、お客さんがたくさん来られるコンクールもあります。
そんな中で、1位、2位という結果だけでなく、「あなたの音楽好きだよ!」と言ってくれる人に出会えることもあります。
わたしは学生時代に受けたコンクールで、匿名掲示板に「なんで◯番が通ったのかわからない」と批判されたこともあります。
でも、同じときに「◯番ははじめの音から全然違った。別の楽器かと思ったくらい。とても良かった」と書いてくれる人もいました。
また、十年以上たってから「◯◯コンクールの演奏、おぼえてます!」と声をかけていただくこともあります。
批判も共感も、とても心に残り、いまでも思い出すことがあります。
そして現在は聴く立場ですが、強く印象に残った人の演奏と名前はおぼえています。
それは優勝者のこともありますが、賞に入らなくても印象に残っている人はいます。
数年後、またその人をどこかで見かけたときに、「あ、あのコンクールのときの子だ」と思い出すでしょうし、ちょっとした応援団のような気持ちにもなります。
(声をかけたこともあります→だれかの演奏をいいなと思ったら伝えてみる、という話 )
コンクールで結果を得ることはとても素晴らしいことですが、本当に価値があるのは人の心に残ることではないでしょうか?
あなたの演奏も、もしかしたらだれかの記憶に残っているかもしれませんよ。
それを励みにして、また音楽と向き合って一歩一歩やっていけたら良いのではないでしょうか。
まとめ
この記事では、コンクールの結果をどう受け止めるのか悩んでいる人や、コンクールってなんのための場所なんだろう?と思う人に向けて書きました。
清々しく本番を終えることができますように!
関連記事
コンクールで結果が出なくて落ち込む人へ。これを読んで気持ちを切り替えよう!
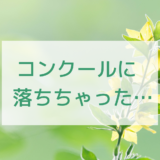 コンクールで落ちた・賞をもらえなくて落ち込むときの対処法
コンクールで落ちた・賞をもらえなくて落ち込むときの対処法
 コンクールになるとこわい・緊張するという人へ~審査員はどんなことを考えている?~
コンクールになるとこわい・緊張するという人へ~審査員はどんなことを考えている?~





