最近、ピアノのコンクールって、ほんとう〜〜にたくさんありますよね。
 もも
もも
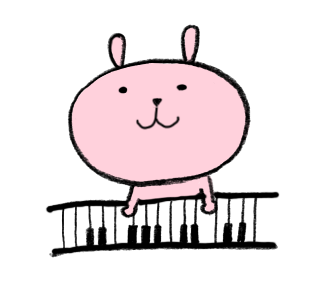 うさぎ先輩
うさぎ先輩
どのコンクールを受けるか?
というのは、あなたも悩まれたことがあるかもしれません。
いろんな角度から検討する必要があるので、むずかしいですよね。
長い時間をかけて準備するので、せっかくなら良い経験になるコンクールを選びたいですし。
検討するには、ふだん習っている先生に相談するのが一番です。
ですが、相談する人がいない方や、自分でも調べてみたい…という方に向けて、この記事でコンクールの調べ方や検討方法をすこしご紹介しますね。
もくじ
コンクールの調べ方
基本的には、このような流れでコンクールを選び、決定することになると思います。
コンクールを調べるには、以下の方法があります。
- 先生やまわりの人に聞く
- 本で調べる
- インターネットで調べる
- 楽器店などで調べる(チラシ・要項が置いてあることが多い)
 もも
もも
日本国内や海外のコンクールの情報がくわしく入った一冊です。
毎年買わなくても、数年間は使えますよ(日程や課題曲などはその都度公式サイトなどで確認しましょう)。
コンクールを検討するときのポイント
気になるコンクールがいくつか出てきたら、内容をくわしく検討していきます。
以下のポイントはとくに注目してみてください。
- 日程・会場・内容があなたのスケジュールに合っているか
- 課題曲はあなたの演奏力に合っているか
- あなたを成長させてくれるコンクールかどうか
- あなたに合うコンクールかどうか
くわしく書いていきますね。
日程・会場・内容があなたのスケジュールに合っているか
まず、日程や会場があなたのスケジュールに合っているかは大事ですよね。
それから、準備する曲の数や規模によっても、受けやすさや大変さが全然ちがいます。
- コンクールを直近の第一目標にする
- 長期的な目標のための練習として受ける
- 学校や勉強、部活と並行して受ける
などで予定も変わってきますよね。
あなたの受けやすいものを選んでくださいね。
 コンクール期間は進度が遅れがち?課題曲だけ練習するのはもったいない!
コンクール期間は進度が遅れがち?課題曲だけ練習するのはもったいない!
課題曲はあなたの演奏力に合っているか
課題曲や選択曲がある場合、あなたの演奏力に合っているか検討します。
- ちょうど良いレベルの曲
- ちょっと背伸びして頑張れそうな曲
- 弾いたことがある曲
などの場合、受けやすいですよね。
(弾いたことがある曲を再度やるかどうかは、場合によりますが)
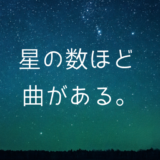 コンクールやレッスンの選曲ポイント〜4つのケース別考えかた〜
コンクールやレッスンの選曲ポイント〜4つのケース別考えかた〜
あなたを成長させてくれるコンクールか
そんなの、受けてみなきゃわかんない・・・かもしれませんが。
- じっくり向き合える曲を演奏できる
- これまでの参加者や入賞者のレベルが高く刺激になる
- 講評をもらえる
- 尊敬する・あこがれのピアニストや先生が審査している
- 審査員によるマスタークラスなど、付加価値がある
コンクールのレベルは、実際に聴きに行くと感じられますし、入賞者のその後の活躍などからもある程度想像することができます。
それから、審査員が尊敬できる人というのも大きいですよね。
審査員から直接アドバイスをもらえるコンクールもあります。
ただ、あくまでこれらはひとつの要素で、成長できるかどうかはあなたの取り組み方にかかってきます。
あなたに合うコンクールかどうか
これは、もっとわからないですよね(汗)
合ってるかどうかなんて、受けて数年、数十年たって気づくことかもしれませんし、そもそも、合う合わないという概念があるのかどうかよくわかりません。
でも、わたし個人の考えとしては、「あんまり受けなくてもいいんじゃないかな…」と思うコンクールがあることも事実です。
- 審査基準にあまり共感できない
- 講評の内容に共感できない
- 参加料がやたら高い(内容にもよりますが)
わたし自身、コンクールを聴きに行っても毎回予想通りの結果になるわけではありません。
時によって結果が変わるのは当たり前ですし、わたしの勉強不足の面もあると思うのですが、コンクールによっては「うーん…なぜ?」と思ってしまうこともあります。
そういうコンクールは、あまり生徒さんにはすすめないですね。
本番経験のために受けるのは良いかもしれませんが。
そのほか、バッハの解釈で、楽譜に書かれたリズムと当時の慣習がちがうことを考慮して弾いた演奏に対して
「リズムが違います。楽譜どおり弾きましょう」という講評をもらってきたときも、「うーん」と思いました。
 コンクールの結果に納得できない?それって自然なことです。審査員でもわからない。
コンクールの結果に納得できない?それって自然なことです。審査員でもわからない。
まとめ
この記事では、
- ピアノコンクールの調べ方
- どのコンクールを受けるかの検討ポイント
をご紹介しました。
最終的には、あなた自身がどのように本番に向き合っていくかがいちばん大事で、コンクールはあくまでひとつの通過ポイントだと思います。
「このコンクールに向かってがんばろう!」と決めたら、音楽に向き合い、曲と仲良くなって充実したピアノ時間を過ごしてくださいね!





