速い曲が弾けない、音色やタッチが雑な演奏になる・・・そんな悩みをもつ人に、よく「ゆっくり練習しよう」と言われますよね。
でも、ただ遅く、ゆっくり弾いていませんか?
ほんとうは、あなたの悩みに合わせて、
・ゆっくり弾く練習
・速く弾く練習
・部分的に速く弾く練習
そして、それぞれの練習は、目的を理解して、だいじなポイントをしっかりと意識して練習することが必要です。
たとえばスピーチや朗読をすることを思い浮かべてみてください。
- 一文字、一単語ずつ読んでも流れの良いスピーチにならないとき
→短い文章に区切ってエイっと速く読んでみる。=速い練習が有効
- 発音がはっきりしない、曖昧にしてしまっている部分があるとき
→その部分だけをゆっくり読んだり、口を大きく動かしたりする練習=ゆっくりの練習が有効
- 速いスピードで発音する単語
→実際にそこだけ速く、しゃべってみる=部分的に速い練習が有効
この記事では、
- ゆっくり練習、速い練習のメリットやポイント
- こんなときはゆっくり。こんなときは速い練習!という、ケースごとの提案
- さらにレベルアップ!リズム練習や分割練習の方法
について 詳しくご紹介していきます。
練習方法に悩むあなたの役に立ちましたら幸いです。ゆっくりとお読みください。
※ゆっくり、速く=この記事では演奏のテンポ(速度)を遅く、速く の意味で書いています。
もくじ
1. ゆっくり練習!メリットや気をつけるポイント
ゆっくり弾く練習。
ほどよくゆっくり、の場合と、すご〜〜〜くゆっくり、の場合があります。
ゆっくり練習は、音を聴けてタッチにも気を配れる

わたしはレッスンで、ゆっくり練習をよくすすめます。
メリットや効果がたくさんあるからです。
〜ゆっくり練習のメリット〜
- 音をよく聴ける
- 音の中身を確認できる(和音の一つ一つの音がわかったり、前後の音との違いがわかったり)
- バランスや響きを聴ける
- 細かなアーティキュレーションを意識できる(どのくらいレガート?どのくらい音を離す?)
- 楽譜の細かい指示を見ながら弾ける
- 指を置いておく、離す、などをしっかり観察しながら弾ける(タッチ・技術的な面)
※お気づきかもしれませんが、これは「ただ単にゆっくり練習」するときにはできません。
「意識を持って、とても丁寧にゆっくり聴いて弾く」ときに、可能になります!
こんなときには、ゆっくり弾いて練習しよう
こんなときに、ゆっくり練習はとても有効です。
ぜひやってみてください。
- いつも速く弾いて、途中でミスしたり音が読めなくなったりして止まってしまうのが癖になっているとき
- 弾くことに必死になってしまって、自分の音を聴けていない、音楽の流れや魅力を感じる余裕がないとき
- 速く弾くのが習慣になって、弾けていない音を飛ばしてしまっている、弾いたとしても「ただ弾いてるだけ」になってしまっているとき
- 技巧的に難しい場所や、思ったような音が出せない部分で、分解して考える必要があるとき
ゆっくり練習のポイント
ゆっくり練習では、次のことに気をつけてみてください。
なんのためにゆっくり練習しているのか、よく意識する
なんの練習でもそうですが、
「なぜその練習をするのか?」「この練習をした後にどうなりたいのか?」
と、目的と目標を明確にすることが大事です。
- 譜読みを確実にしたいから?
- 指の動き・タッチを丁寧に確認したいから?
- 一つ一つの音をよく聴いてみたいから?
「テンポ」以外は、ゆっくりなのか?速くするのか?を確認しておく
- 「動作」はゆっくりなのか、速いのか?
- 「タッチ」はゆっくりなのか、速いのか?
ゆっくり練習していても、ポジションの移動は素早いほうが良かったりします。
すべてが「ゆっくり」とも限らないわけですね。
よくわからないときは、先生や信頼できる人についてもらう
ゆっくり練習は、集中力や「聴く・判断する」力が不可欠です。
自分で聴いて考えながら練習できることがベストですが、いきなりできることではありません。
ぜひ誰かに頼りましょう。
わたしのレッスンでも、何にどう気をつけてゆっくり練習するのかについては、かなり細かく一緒にやっています。
それで同じようにお家で練習してくれれば良いのですが、1回で100%ともいきません。
コツコツ繰り返していきます。
あるとき、「すごく丁寧に練習してきてくれた!!」と感激することがあります。

実は、わたし自身もそうです。
小さい頃はゆっくり練習なんてつまんないや〜と、あまり好きではなかったのですが、
ゆっくり一つ一つ自分の音を聴く、ということを 高校・大学時代に本当に根気づよく先生から教えていただきました。
その教えはいまも大切にしています。
2. 速く弾く練習!メリットや気をつけるポイント
では次に、速く弾く練習についてです。
この場合の「速く」とは、実際にその曲を演奏するテンポ、ときにはそれ以上の速さも含みます。
速い練習は、音楽の流れや世界をつかみやすい
〜速い練習のメリット〜
- 音楽の流れをつかみやすい
- フレーズの長さや、方向性を見つけやすい
- 和声の繋がりを感じやすい
- 実際の曲のすがた・イメージを感じながら練習できる
- 「速く動かす」練習そのものに意味がある(エチュードや速いパッセージ、連打など)
- 指や体の、実際の動きを確認できる
また、物理的にも、体の動きが実践的であるというメリットがあります。
※ただし、そのテンポでやろうと思ってもできないこと、動かしたいのに動かない、というようなときに、やはり工夫した練習が必要になります。
こんなときには、速く弾く練習をしてみよう
音楽の流れや全体の把握のために
曲の全体を感じたいときに、速い練習はとても意味があります。
- 真面目にきちんと一音ずつ弾いているが、どうも流れがないとき
- 視野が狭くなっていたり、フレーズ感が短くなったりしているとき
- 長い呼吸や方向性がよくわからない、できないとき
- ゆっくりから譜読みを続けてきて、弾けるようになったが速いテンポで弾いたことがないとき
- もともと遅いテンポの曲だが、全体を見渡すために、実際に弾くテンポより速く弾いてみる
リズムやキャラクター、イメージの確認のために
 まだ全部を速く弾けなくても、「この曲、速くなったらどんな感じなんだろう?」と知っておいたほうがいいです。
まだ全部を速く弾けなくても、「この曲、速くなったらどんな感じなんだろう?」と知っておいたほうがいいです。
- そのフレーズがもつキャラクターを確認したいとき
- リズムのもつ特徴を確認したいとき
これらはゆっくり〜中くらいの速さで何度も練習していても、つかめません。
思い切って速く弾いてみて、「あ、こんな感じなんだ!」とイメージがわいてきたら、また別の練習をしてみましょう。
技術の習得・実感のために
技術を上げるには、ゆっくりきちんと練習!と思われる方もおられるかもしれませんが、
実はそれだけでは足りません。
「速く」動かすということが必要です。
弾けない場所がある、テンポが上がらない、というときには部分的に「速い」動作を確認し、実感することが必要です。
これについては、下の「2−2」の項目でさらに詳しく書いていきます。
速い練習のポイント

何のために速く弾いているかを確認
ゆっくり練習のときと同じです。
「目的」がとても大切です。
・曲の流れを見つけるのであれば、多少のことは気にせずに、とにかく全体を感じて弾きます。
・技術の習得のためであれば、その部分に最大限集中して、試してみます。
2-2.【重要!】部分的にテンポを速く弾く練習

「2.速い練習」の補足ですが、とても大切な部分です。
一部分だけを取り出して速く弾くことについてです。
3つご紹介します。
リズム練習は、目的意識をもって取り組む
よくある「リズム練習」。
先生に「リズム練習してね!」と言われる人も多いのではないでしょうか。
すべてを速く動かすことが何らかの理由でできないときに、速い部分と、そうでない部分を組み合わせたリズム変奏をする練習です。
リズム練習をするときには、強い意識が必要です。
たとえば「ターータタ」のリズムで弾くときに、「タタ」の部分はこのような動き・音で弾く!確認する!と思って練習するのです。
なんとなく「何回かターータタでやってたら弾けるようになるかな」というわけでもないのです。
分割練習
いくつかの音、音節ごとに区切って速く弾く練習です。
エチュードや技巧的な部分では、ぜひやってもらいたい練習の一つです。
8個の音を素早く動かすのが難しい場合、2つ、3つ、4つ、8つなどと区切って速く弾きます。
そこで指の速度や体の動きを確認していきます。
間を空ける練習
ある部分まで速く弾く→ふだんより「間」を空ける→次の部分から、また速く弾く
という練習です。
「間」を空ける部分で、跳躍の確認や、次の音の準備動作の練習をします。
- 跳躍の場所
- ガラッと雰囲気や弾き方が変わる場所、
- ベートーヴェンのソナタなどによく出てくる「subito p」(ただちに弱く)の場所
また、場面が変わるギリギリの場所までしっかりと弾ききる練習にもなります。
まとめ:いま、どんな練習が自分に必要か?を見きわめる
ここまで、ゆっくり練習と速い練習についてまとめてきました。
どの練習にも、良い点と、気をつけなければ意味がない点や、逆効果になってしまう点があります。
とくに、速い曲になればなるほど、「ゆっくり」弾くときと「速く」弾くときで、
全体の流れ、リズムの感覚や体・腕の使い方、エネルギーの通り方が違いますので注意が必要ではあります。
お薬と同じで、使いどころと使い方を見きわめることが大切です。

いろいろな視点から、ぜひためしてみてください。
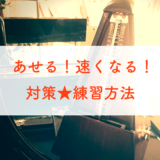 ピアノの本番で緊張してあせる、速くなる人へ。失敗を防ぐ練習方法は?
ピアノの本番で緊張してあせる、速くなる人へ。失敗を防ぐ練習方法は?
 ハノン・スケールとアルペジオの使い方。ただの指練習じゃない!
ハノン・スケールとアルペジオの使い方。ただの指練習じゃない!




