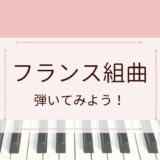ピアノを習う人なら誰しも通る道?
ツェルニーの練習曲集。
- ツェルニーつまんない。
- ツェルニー嫌い。
- ツェルニーなんて時代遅れ?やらなくてもいい!
- 何のためにやってるの?
- ツェルニーがしんどいから、ピアノのレッスンが嫌になってきた…
そんな、いろんな声を聞くこともあります。
そこでこの記事では、ツェルニーで学べることをまとめてみました。
ものすごくざっくりと言えば、
- 古典派のソナタの演奏の基礎
- 各曲の中で断片的に出てくる技術的なパッセージを演奏するための基礎テクニック
- 基本的な和声感覚
- 曲を分析して演奏するための基礎力の一部
- 技術的な要素を、美しく華やかに弾くための技術や耳、音色
を養えます。
※おもに30、40、50の練習曲集を想定して書いています。
※ツェルニーでなきゃ絶対ダメ、という話ではありません。
「何のためにやっているか」がわからないことって、苦行ですよね。
もう一度ツェルニーの目的や活用方法を再確認してみませんか?
もくじ
ツェルニーの練習曲で何が学べるの?
ツェルニーで学べることを、大きく4つに分けて解説します。
- 様々な曲を演奏するために必要なテクニックを習得する
- 基本的な曲の構成・和声進行の知識や感覚を身につける
- シンプルな曲も音を磨き、魅力的に弾く意識や耳・音色を身につける
- 今後弾く「むずかしい曲」にどう取り組むか、練習の習慣や考え方を身につける
さまざまな曲を演奏するために必要なテクニックを習得する
あなたも、「ツェルニーは指の練習曲!」という認識を強く持っていると思います。
さまざまな曲を演奏するために必要な、いろいろな技術を学ぶことができます。
- スケール
- アルペジオ
- 和音をつかむ
- 伴奏形
- 細かい音型
- さまざまなリズムパターン
- 跳躍
- トリル
- アーティキュレーション
- fで弾く
- pで弾く
曲を弾いていて「あ、これツェルニーの◯番と同じ形だな」と気づくことは多いです。
ベートーヴェンのソナタをはじめ、あらゆる曲で出てきますよ。
シューベルトの歌曲伴奏でも、「あ、この形!」と思うことがありました。
もちろんその曲独自の世界観、表情の中で各技術を練習していくのも大事なのですが、
「その音型を無理なく弾ける技術は、すでに身についている」
というのは強いです。
余裕が出ますよね。
基本的な曲の構成・和声進行の知識や感覚を身につける
ツェルニーの練習曲は、とてもわかりやすい構成で書かれています。
- A- A’ – B – A” などの構成
- 2+2+4=8小節、など、見つけやすい単位のフレーズ
- サブドミナント→ドミナント→トニックなど、基本の和声進行
- 近親調への転調や、コーダの終止形などの特徴的な和声進行
- 同じモチーフの繰り返し、変奏
- 右手と左手の交替
構成にしっかり注目して、どのようにまとめたら良いか?と考えて演奏します。
また、そういうことを感じながら何曲も重ねて弾いていくと、だんだんその感覚が耳や体にしみ込んでいきます。
長い曲を分析したり、大きく見てまとめたりする土台のひとつになります。
シンプルな曲も音を磨き、魅力的に弾く意識や耳・音色を身につける
ツェルニーってつまんない?
たしかにドラマは少ないかもしれませんが、意識や練習方法を変えれば、少なくとも今よりはもっと素敵に弾くことができると思いませんか?
つまんなく弾くと、ほんとにつまんない演奏になっちゃいます。
わたしはレッスンでツェルニーを扱うとき、
- 30番まではテクニックと構成重視でしっかりまとめること
40番に入ったら、
- 美しく弾くこと
- 華やかに弾くこと
- 曲として魅力的に弾くこと
もちろん30番のときから美しく華やかに弾くのは理想なのですが、まだ余裕がないことも多いので、こだわりすぎずポンポンと進めていきます。
(とはいえ40番も技術的な課題がどんどん現れるので、余裕をもって弾くのはなかなか難しいですけどね・・・少しでも意識してもらえたらいいなと思っています)
今後弾く「むずかしい曲」にどう取り組むか、練習の習慣や考え方を身につける
ツェルニー40番をきちんと終える頃には、ベートーヴェンやショパンやリスト、ちょっと背伸びした曲や技術的にもむずかしい曲にチャレンジすることも増えてくるでしょう。
がんばって練習していても、ここがどうしても弾けない…
そういう悩みも増えてきます。
そんなとき、ポイントを絞った「効果的で必要な練習方法」を考えて実践していくことも大切です。
ツェルニーを練習している頃から、
- この曲の技術的なポイントは何か?
- 自分の技術的な問題点はどこか?
- その課題を効果的に改善していくための練習方法や弾き方、聴き方は?
という視点で練習を重ねる習慣をつけておきましょう。
頑張っている人はこれからますます、大きな曲や長い曲を弾く機会が増えると思います。
そんなとき、技術的にも、また曲を大きく見据えてまとめるという点でも、できるだけ効率よく時間をつかっていくことが大切です。
▼効率的な練習時間のつかい方について
 忙しくてピアノの練習時間がとれない?限られた時間を有効につかうには?【練習編】
忙しくてピアノの練習時間がとれない?限られた時間を有効につかうには?【練習編】
▼ツェルニー40番を使った、「課題に即した練習方法の見つけ方」の話(一部有料)
ツェルニーでは十分に学べないこともある
ツェルニーでピアノ演奏のすべてを学べるわけではありません。
それぞれの曲、教本の特徴がありますので、ツェルニーで足りないものはほかの曲や本で補う必要があります。
- ポリフォニーの理解・演奏
- 和声的に動いていく曲(コラールのような)
- ロマン的な様式・表現
- 近現代のさまざまな様式・表現
まとめ〜ツェルニーが嫌い?目的をもって練習しよう!〜
この記事では、ツェルニーの練習曲で学べること、意識してみてほしいことをまとめました。
ツェルニーのどんな曲も、余裕を持って音楽的に弾けるくらいの力を身につけると、いろんな面でスムーズですよね。
ツェルニーが嫌いでピアノまで嫌いになっちゃう人が、ひとりでも減りますように。
〜こんな記事もおすすめ!〜
 暗譜が苦手な人への対策「ツェルニー/8小節の練習曲」
暗譜が苦手な人への対策「ツェルニー/8小節の練習曲」
 ハノン・スケールとアルペジオの使い方。ただの指練習じゃない!
ハノン・スケールとアルペジオの使い方。ただの指練習じゃない!