この記事では、ピアノ初見試験の対策をご紹介します。
音大受験や音高受験、また学内でも行われることのあるピアノ初見の試験。
でも、初見に苦手意識を持っている人はけっこういると思います。
- 予見時間が足りない。どうしたらいいの?
- テンポ設定は遅くても大丈夫?
- どうしても弾けない場所は止まってもいい?
- 初見で良い演奏・良くない演奏って?
など、気になることもいろいろありますよね。
この記事では、ピアノ初見の試験の対策や気をつけるポイントをくわしく解説していきます。
ピアノ初見の試験では、予見(音を出さずに楽譜を見る)時間が与えられ、その後ピアノで演奏する、ということが多いので、その想定で書いていきますね。
つまり、
- 予見のコツ、ポイント
- 演奏のポイント
予見は1分〜3分くらいのことが多いようですが、とりあえず1分〜1分半くらいで練習していくと良いでしょう。
もくじ
ピアノ初見の試験では、何を見られているの?
初見の試験では、
- ソルフェージュ力
- 読譜力
- 表現力
- 音楽の幅広い経験
- 瞬時の対応力
- ピアノ演奏の基礎的な能力
- 舞台強さのようなもの
など、いろんなことがわかっちゃいます。
この下からは、実践的な対策を書いていきますが、長期的にさまざまな力をつけることも大事なので、いろんな面から磨いていってくださいね。
◎参考記事
 ピアノ初見力アップのためにできること(長期的な対策)
ピアノ初見力アップのためにできること(長期的な対策)
ピアノ初見の試験。予見では何を見ればいい?
まず、曲の基本的な情報を短時間で見る
まず、楽譜の基本的な情報をぱっと見ます。
- 調号、調性
- 拍子
- 小節数、大まかな構成(リピート記号やD.Cがあるか?同じメロディやテーマの部分があるか?)
ここまで、5秒〜10秒で判断しましょう。
どんな曲か?イメージをキャッチする
- 曲のタイプ(例:和声的な曲、ワルツ風の曲、快活で動きのある曲、など)
5秒以内で判断しましょう。
(パッと見て判断するためには、いろんな曲を弾いたり聴いたりしている経験が必要ですよね)
予見するところを判断する(作戦立て&ゆるく読む)
楽譜をはじめから終わりまでざっと大まかに眺めながら、さらに予見する場所を決めます。
はじめからじ〜〜〜っと見ていっても、ほぼ時間オーバーになりますので、とくに見る場所を絞ります。
たとえばこんな場所が、さらに予見すべき場所です。
- 曲の出だし(ただし、易しければじっくり読む必要はない)
- リズムや臨時記号、声部の数など、その前と比べて変化しているところ
- 音が多いところ
- 曲の盛り上がりと思われるところ
ゆるく読みながら、なので10秒くらいかけて良いと思います。
ここまでで20〜25秒ですね。
予見1分〜1分半なら、このくらいのペースでいきたいです。
予見時間が3分くらいあれば、それぞれ少しずつ長めに時間をとって良いです(予見3分ということは、かなり複雑な課題だと思いますので…)
実際の音符を見ていく。7分目くらいで!
「ここを読むぞ」と決めたところを読んでいきます。
でも難しい課題を見ると、「こんなの、絶対間に合わない!」と焦っちゃいますよね。
ポイントは、7分目くらいにしておくことです。
それぞれの場所を全部理解しようと思うと、けっこう時間がかかります(しかも緊張しているとあっという間に時間が過ぎてしまいます)。
そのため、7分目くらいまで情報を先に取り入れておき、残りは実際に弾くときに読みながら弾きます。
こんなイメージです。
- ややこしいところは、外声だけは確認しておく
- 左手の和音は見ておいて、右手のメロディーは弾きながら読む
- リズムが複雑そうなので、リズムだけ確認しておく
でも、全部10まで完璧に読もう〜としていると、ほぼ時間オーバーになります。
7分目くらいで切り上げる勇気をもってください。
自分の初見力に自信を持てれば、「このくらい事前に読んでおけばきっと弾ける!」と思えて切り上げることができるかもしれません。長期的に鍛えていきましょう。
いざ!演奏するときに気をつけること
制限時間いっぱいになると、ピアノの部屋に移動して「はい、では弾いてください」などと声をかけられると思います(ピアノの前で予見することもあります)。
声がかかったら、すぐに弾きましょう。
「まだいつまでも読んでるな」と思われると悪印象です。
(一呼吸おいて、3〜5秒以内くらいかな?)
弾き始めるときに気をつけておいたほうがいいことがあります。
それは、
- テンポ設定
- 音楽のベース(土台)を持って始めること(調、拍子、大きな流れ)
この下で解説していきます。
テンポ設定は重要!
まず、テンポ設定を間違えると、修復が難しいです。
速すぎると途中で弾けなくなりますし、遅すぎても音楽が止まってしまいます。
難しいところですが、「余裕をもって弾けそうな速さ」「音楽の流れが保てる速さ」の交わる点のテンポが良いですね。
速度指示があればそれも考慮します。
よくある質問コーナー「テンポ設定について」
突然ですがここで、よくある質問コーナーです。
AllegroやAllegrettoと書いてあっても、速く弾けなさそうだったらゆっくり弾いてもいいですか?
…悩むところですね。
Allegroと指示があっても、速くて弾けないようなテンポで始めてぐちゃぐちゃになると困りますよね。
でも、ゆっくりすぎると、曲のキャラクターを無視した演奏になってしまいます。
難しいところですね!
そんなときは、遅めのテンポにするけど、曲のキャラクターはAllegroらしくするのがおすすめです。
活気のあるリズム感で弾いたり、打鍵のスピードを速めにしたり。
遅くても、遅く感じさせない演奏がいいですね。
音楽のベース(土台)である調・拍子・流れを自分の中に持って弾く
ここで言う音楽のベースとは、低音の意味ではなく、音楽の土台のようなものです。
わかりやすく言うと、
- 調
- 拍子
- 大きな流れ
たとえばA-durならA-durの感覚をもって始めます。
ひとつひとつの音をゼロから読むのではなく、A-durの調を体の中にもって弾くと格段に読みやすくなります。
たとえば、
「なんて書いてある? shirayukihime」
と
「ローマ字ですよ。 shirayukihime」
ローマ字という前情報があったほうが、速く意味がわかりませんか?(ちょっとのことですが)
そして読みやすいだけでなく、これらのベースをもって弾き始められれば、多少のミスや読み間違いがあったとしても、音楽的な演奏になります。
というか、そうでないと音楽にならないんです。
初見が苦手な人は、調や拍子、音楽の流れが薄い中で、音を読んで弾いていってしまいます。
英語なのか日本語なのかわからずに、「si」とか「ra」とか発音しているような感じで、音楽的なまとまりや説得力が出ないんですよね。
ふだんから調性感や拍子感を意識して演奏したりして、基礎力をつけておきましょう。
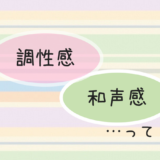 調性感・和声感のある演奏に必要なこと
調性感・和声感のある演奏に必要なこと
読みながら弾いていく!コツはあるの?
先ほども書きましたが、読みながら弾いていきます。
音の羅列ではなく、音楽として成立させるためには、「流れ」がとても大事です。
止まらずに弾きましょう。
そのためには、こんなことに気をつけてください。
- 音を出しながら、目は次の小節や次の段を早めに見ていく
- 10ではなく8〜9をめざして弾いていく
- 瞬時に全部読めなくても、大事なライン・要素だけは確実に出す
8〜9割方弾きながら大きな流れに乗っていくイメージです(難しい曲なら7割くらいでもいいかもしれません)。
よくある質問コーナー「どうしても弾けない!という場所でどうしたらいい?止まっちゃダメ?」
ではまたここで、よくある質問コーナーです。
どうしても予見が間に合わなくて、弾けそうにない場所があります。
ぐちゃぐちゃでも、片手だけになっても止まらないほうがいいですか?
それとも、止まりながらきっちり弾いたほうがいいですか?
これまた難しいところですよね。
先ほど書いたように、流れを大事に音楽を進めていきたいので、弾き直しはできるだけ避けたいです。
かといって、止まっちゃダメだし!と思うがあまり、
- 一番上の音だけザーッと弾いてしまったり
- わけがわからなくなって、ぐちゃぐちゃの音を出してしまったり
となると、これも音楽ではなくなってしまいます。
そこでおすすめなのは、
流れを止めずに、少しゆったり(大事に)弾くことです。
テンポを遅くしたり、細かく数えて読んだりしたほうが音そのものは読みやすいので、
聴いている人に気づかれない程度に、その部分だけ少しゆったり弾きます。
その部分だけ、 すこぉぉし ゆ〜〜った り 弾きます。
↑こんな感じでしょうか(笑)
実際は、こんな理想どおりに行かないこともあると思いますが…できるだけ、心がけてみてください!
初見演奏でも音楽的な演奏にするためには?
ここまで、初見演奏の予見と演奏のポイントを書きました。
すべての音をぱっと完璧に読んで弾ける人もごく一部いますが、普通はなかなかそうもいかないと思います。
だってさっき見たばかりの、初めての楽譜ですよ?
そりゃ大変ですよね。
それに、試験課題の中には「こんなん無理やん」みたいな曲もあります…。
だから、肩に力を入れず、大体読めたらいい!と大らかにとらえて弾いてください。
でも、初見演奏であっても音楽的に弾くことはとても大事です。
初めて見た楽譜でも音楽的に弾くにはどうすればいいでしょうか?
それは、
音楽に対して、いつでも大切に接する習慣をつけることです。
ひとつのメロディー、ひとつのリズム、ひとつの和声進行。
いつでも、音・音楽を大事に扱って演奏する習慣。
そういうのが、いざというときの演奏に出てきます。
実践的な試験対策をしつつ、ふだんから音楽を大事にしてくださいね!
試験対策におすすめの曲集
最近、レッスンで初見の試験対策をするときに使った楽譜をご紹介します。
これは一例ですので、どんな曲集でも応用できるかと思います。
プロコフィエフ つかの間の幻影
近代的な和声、臨時記号やさまざまなリズムの体験にちょうど良いです。
音高入試対策くらいでしょうか。
モンポウ ピアノ作品集
大学入試対策くらいにちょうど良かったです。
高額なので、初見の練習だけのために買うならおすすめしません!
モンポウの「歌と踊り」「沈黙の音楽」などを弾いてみたい、興味がある、という人におすすめです。
バッハ 小プレリュードとフーガ
カッチリと楽譜が読めない、古典的なスタイルの楽譜を見ると緊張してしまう・・・という人にはこういう曲を初見で弾いていくのも良いかと思います。
まとめ
この記事では、ピアノ初見の試験対策方法をくわしく書きました。
わたしの経験から来る「さいりえ式」なので、誰にでも最適かどうかはわかりませんが、できるだけ具体的・実践的に書きました。
あなたに合う部分があればやってみてくださいね!
〜あわせて読みたい記事〜
 ピアノ初見力アップのためにできること(長期的な対策)
ピアノ初見力アップのためにできること(長期的な対策)
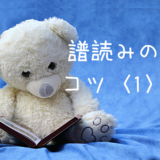 ピアノの譜読みが速くなるコツは?【第1回】今日からできる!対策&練習方法
ピアノの譜読みが速くなるコツは?【第1回】今日からできる!対策&練習方法






